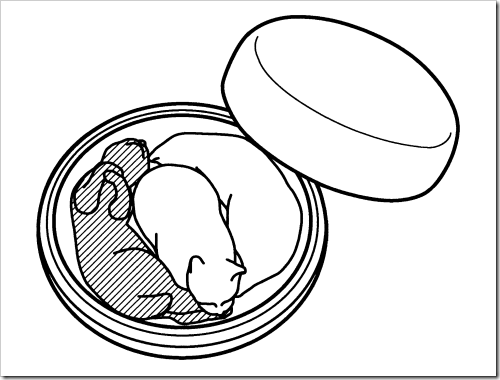サーバ製品の発表イベントのために来日していた米HPのIndustry Standard Servers 部門シニアバイスプレジデントのMark Potter氏にインタビューしました。同氏は、Compaqのエンジニア出身、HPのアナリストイベントでは私も何回かインタビューしていますが、技術者出身らしくテクノロジー好きの気さくなお人柄の方です。

栗原「今回のポッターさんの来日の目的を教えてください。」
Mark Potter「HPの新世代IntelサーバであるProLiant Gen8の発表イベントでの基調講演などが主な目的です。」
栗「新世代サーバで特に新しくなったのはどのような点でしょうか?」
ポ「基調講演ではMoonshot、Odyssey、そして、VoyagerというHPで進行中の3つの重要なプロジェクトについてご紹介したので、製品個別の話をするよりも、それに沿ってお話ししましょう。まず、Moonshotですが、これは、エネルギー効率性を大きく向上させた新世代サーバ製品のプロジェクトです。ARMやATOMベースのサーバにより、従来と比較してエネルギー商品を80%から90%改善し、設置スペースを10分の1にするのが目標です。」
栗「ハード基盤のプロジェクトと考えてよいですね?」
ポ「基本的にはそうです。Odysseyも基本的にはハードウェア・プラットフォームのプロジェクトです。”Misssion Critiacal for Masses”がモットーです。4年前にIntegrity系サーバ製品がブレード化され、Xeon系サーバとフォームファクターが統一されたのはご存じと思いますが、その延長線上にあるものです。Unix系、Liniux系、Windows系、さらには、NonStopやOpenVMS系のサーバを共通化していくのが目標です。」
栗「X64上でのHP-UXサポートも計画に含まれているのでしょうか?」
ポ「それについては公式にはそのような計画はないとだけ申し上げておきましょう。さて、今回、一番強調したいのはプロジェクトVoyagerです。これは、ハード、ソフト、サービスを包含する広範なプロジェクトです。3億ドル以上の投資と2年以上にわたる研究開発の成果であり、今後のサーバ市場を再定義するだけのインパクトがあると考えています。Voyagerの大きな目標としてライフサイクル全般にわたった管理性の向上があります。たとえば、システムの障害情報をクラウドベースのサービスで自動的に収集しており、特定のロットの部品に障害が多いということが判明すれば、障害が発生する前にプロアクティブに交換を行なうことができます。」
栗「メインフレームでは昔から似たようなやり方をやっていますね。」
ポ「おっしゃるとおり、過去においてはメインフレームの世界で限定的に行なわれていたことを業界標準サーバの世界にも拡張したと考えてください。」
ポ「また、細かな工夫ではありますが、きわめて微細化しているCPUのピン損傷を防ぐためにHP独自のSmart Socketという技術を開発しました。マザーボード障害の多くがCPUピンの曲がりに起因していることがわかったからです。また、ディスクドライブのキャリアにもデータ系とは別の制御系のコネクタとLED表示を設けており、リビルド中のドライブを誤って抜いてしまうようなエラーを防いでいます。また、性能面でもアレイコントローラーにはHP独自のブレークスルーがあり、性能向上に貢献しています。これは、SPEC Virtualizationベンチマークの結果を見ても明らかです。このような細かな改善の積み重ねがお客様に価値を提供すると考えています。」
栗「最後に、POD(Performance Optimized Datacenter)(注:コンテナ型データセンターのこと)についてお伺いできますか?」
ポ「はい、PODも私の担当製品です。HPのPODは水冷という点がユニークな存在です。これにより、1.06という驚異的なPUEを提供可能です。つまり、機器冷却により無駄になる電力がほとんどありません。ご存じと思いますが、一般的なデータセンターではPUEが2.0、つまりデータセンターに供給される電力の半分近くが冷却等のオーバーヘッドに費やされてしまうこともあります。」
栗「最近はあまりグリーンITという言葉を聞くことも少なくなりましたが、やはり消費電力削減のニーズは依然として大きいのですね?」
ポ「米国では電力効率性に関する注目度はますます高まっています。コスト上の理由もありますし、データセンターの電力効率性に関する当局の規制がますます強まることが予測されているからです。」
栗「他社のコンテナ型データセンターではISO規格の標準コンテナをそのまま使っている点をセールスポイントにしているところもあると思うのですが。」
ポ「HPのPODは水冷ということもありISO規格のコンテナをそのまま使っているわけではありません。ただし、基本的なサイズやフックの位置は同じです。なので、運搬時に問題になることはほとんどありません。」
栗「PODのユーザーは増えているのでしょうか?」
ポ「もちろんです。すべてのユーザー事例を公開できるわけではないのですが、最近の例ではAirbus社の事例があります。HPC(科学技術計算)に使用しています。また、マイクロソフトのデータセンターの一部でも使われています。」
栗「コモディティ化が相当に進行している業界標準インテルサーバの領域でこれだけのイノベーションを実現できるというのはすばらしいことですね。」
ポ「『コモディティ』という言葉は考えないようにしています。この分野は『コモディティ』なんだと思ったとたんにお客様のことを考えなくなり、イノベーションの動機付けがなくなってしまいます。『標準に基づいたイノベーション』(Innovation on Standards)こそがこの分野におけるHPのモットーです。」
栗「素晴らしいモットーだと思います。本日はどうもありがとうございました。」
【栗原の感想】
コモディティ化が極限まで進んでしまったインテルサーバの世界で差別化を提供しようとするならば、「規模の経済」による効率性、そして、システム管理面での強化くらいしか残っていないと思いますが、HPはまさにその道を突き進んでいると言えます。市場カテゴリーとして見れば、IAサーバ市場は決して成長市場ではないですが、もちろん衰退市場でもないので、当面、HPの強力なポジションは揺るがないと思います。
【こぼれ話】

このインタビューはセミナー会場のホテルで行なっていたのですが、インタビューの後に、ポッター氏が「現物を見た方がわかりやすいだろうからデモ機で説明しよう」ということで、展示会場まで行って直々に説明していただけることになりました。写真には撮れませんでしたが、ハードディスクのキャリア、ラックのマウント部(耳)、電源ケーブルなどに、すべて制御用のコネクターが設置されています。これにより、ラックにどのような機器がマウントされているか、この機器はどの電源系統に接続されているか等々がわかるようになっています。なお、普通の電源ケーブルを使用することも可能ですし、HP以外の機器をラックに搭載することも可能です。まさに、Innovations on Standardsです。
私に熱心に説明しているポッター氏のことをデモンストレーターだと思ったのか、まったく関係ないお客さんが質問してきました(その時は私も「あれ次の枠にインタビューが入ってるプレスかアナリストの人なのかな?」と思っていたのですが、そうではなく一般客の人でした)。しかし、ポッター氏は、依然としてうれしそうに質問に答えていました。氏のお人柄が伺い知れます。質問した人もまさかこの人がHPの上級役員だとは思いもしなかったでしょう。