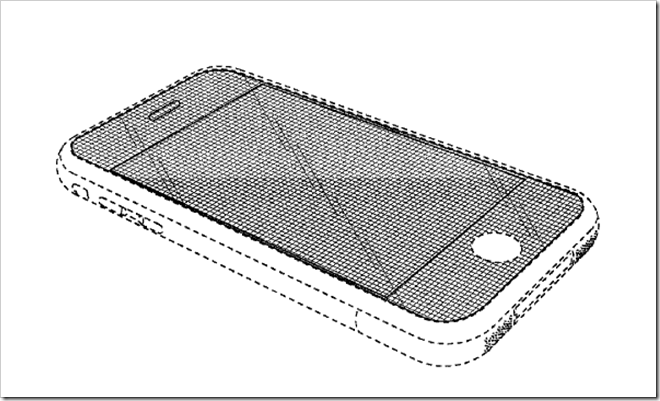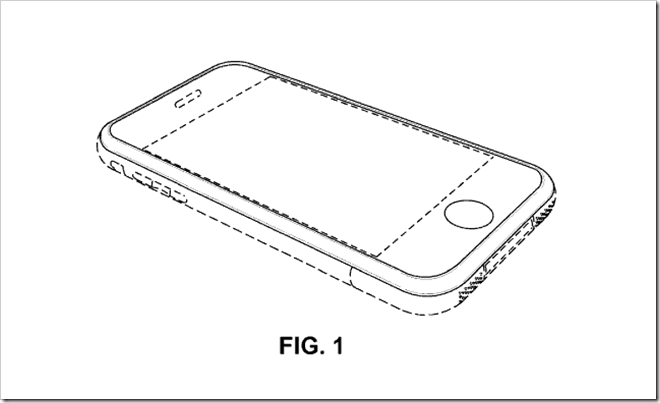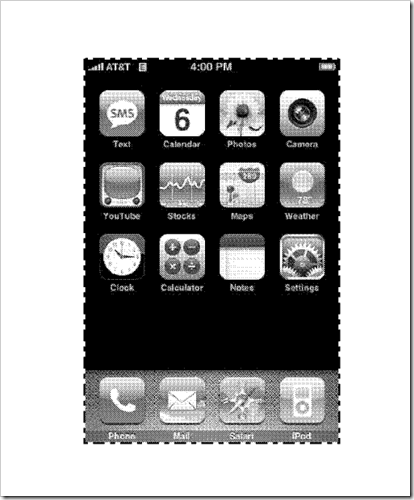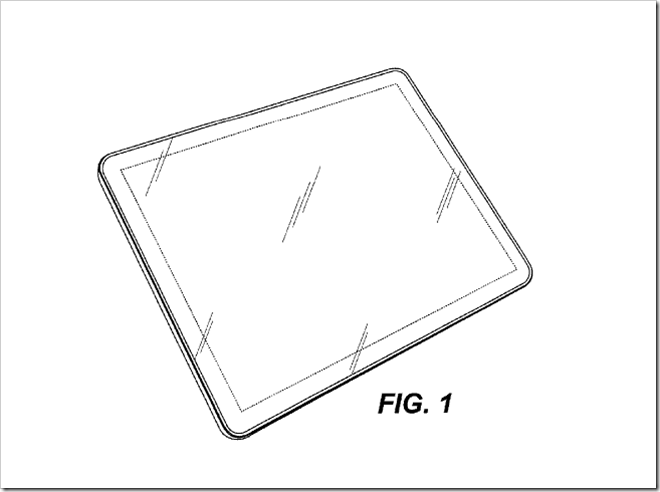アップルvsサムスンの日本での裁判ですが、なかなか正確な情報が出ず、カリフォルニア地裁の裁判とはそもそも争点になった特許が違う(しかも、スマートフォンの本質的機能とは直接関係ない特許であった)点がすぐには明らかになかったため(当ブログでは可能な限り正確にお伝えしましたが)、「アップルが米国では勝ったのになぜ日本では負けたのか」みたいなピント外れな分析をしている記事やブログが見られました。
日本における裁判間連の情報収集は実際に傍聴するか裁判所まで出向いて資料を閲覧しない限り、メディア経由の二次情報に頼るしかない(しかも、大手メディアであっても知財間連においてはちょっと怪しげなことが多い)ので困ったものです。(重要な裁判については判決文が裁判所のサイトに公開されますが、タイムラグがありますし、すべての裁判の判決文が公開されるわけではありません。また、判決が出る前の裁判についてはWebで情報収集する手段はほとんどありません。)
たとえば、日本におけるアップルとサムスンの他の訴訟についても、テレ東は「7件の裁判が続いている」と言っていますし、NHKでは「4件の裁判が起きている」と言っており、どちらが正しいのかわかりません。
そもそも、日本では、どこがどこを訴えているかを調べるだけでも大変です。裁判所まで出向けば資料を閲覧できるのですが、そのためには、事件番号を知っていなければなりません。原告、被告名で事件番号の検索はできるのですが、検索端末は自分で操作できず担当者に依頼して検索してもらう必要があるそうです。そうなると、日本法人と本社のどっちが原告・被告なのか等の問題もありますので、網羅的に調べるのは大変です。さらに、コピーは許可されていませんので、内容を持って帰るにはメモを取るしかありません。
これに対して米国ではPACER(Public Access to Court Electronic Records)というサイトがあり、ここで全米の裁判所のほぼ全部の資料が検索可能になっています(ただし、1ページあたり10セントの料金を取られます)。(実費ベースの料金ではあるのですが、有料であることに反発して一度PACERからダウンロードした資料を無料でシェアーしようというプロジェクトRECAPが運営されています(米国では公的資料は著作権保護の対象外なので著作権侵害ではないと主張しています))。たとえば、米国のアップルvsサムスンの資料もRECAPのアーカイブに行けば無料でダウンロードすることができます(アーカイブに蓄積されていない資料はPACERから買うしかありません)。
ともかく、裁判記録、特に、知財関係の裁判記録は社会的にきわめて重要なのでより多くの国民にアクセスできるような仕組み作りが必要だと思いますが、日本はまだ全然できてないと思います。
民事裁判でも離婚や相続に関するものであればプライバシーの問題もあると思いますが、知財関係の場合は結果的に当事者以外に影響が及ぶので公益的な観点から情報公開を促進すべきでしょう(たとえば、ある大手企業に対して特許訴訟が提起されているの事実がわかれば、関連企業はその特許を回避すべく早めに設計変更を行なえるでしょう、これによって無駄な訴訟や開発努力も減らせます)。
ところで、この辺の事情はドイツも同じようであり、知財ブログFOSSPatentsの中の人Florian Muller氏も「自分はドイツ在住なのに、なんでドイツ国内の裁判よりも米国の裁判について詳しい情報を得られるんだ」とちょっと不平を述べてたりしています。