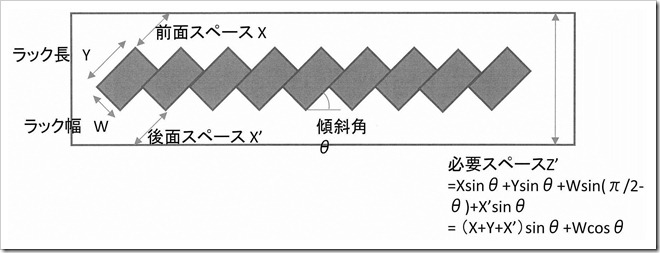10/1から施行される著作権法改正については本ブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。
まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。
誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。
今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。
また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。
誤解2: 今回の改正によりYouTubeの動画を見ると刑事罰の対象になる。
原則として、著作権法は著作物を見たり、聴いたりする行為を直接制限することはありません。ゆえに、視聴行為が違法になったり刑事罰の対象になることはありません。この辺は、文化庁のQ&A(PDF)においても、明確に書かれています(下線は栗原による強調)。
Q4.違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで違法となるのでしょうか?
違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません(以下略)Q5.「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。
なお、ツールを使ったり、キャッシュ・フォルダーからコピーしたりして、YouTube等の動画をダウンロードしてオフラインでも見れるようにするとその時点で(単なる視聴ではなく)ダウンロードしたことになりますので、条件次第では刑事罰の対象になり得ます。
とは言え、ユーザーがダウンロードしてるのか通常の視聴をしているのかは外からはわかりませんので、警察が「わるいやつをこらしめる」ために文化庁とは違う「独自の解釈」でダウンロード刑事罰化を方便として使う可能性が排除できないとは言えます。
誤解3: 今回の改正によりレンタルCDからのリップが刑事罰の対象になる。
これも前に書きましたが、レンタルCDからのリップ(というよりも、自分で聴くことを目的に自分でCDをコピーする行為全般)はCCCDをコピープロテクト解除してコピーするパターンでない限り合法です。これは今回の改正でも変わりません。ただし、一部のネットレンタルでは利用規約で複製禁止になっているものがあるようなので、この場合にはレンタル事業者との間の契約違反にはなるでしょう。
誤解4: 今回の改正により同人活動が制限されることになる。
これは、現在の著作権法の重要論点ではありますが、今回の改正とは関係なくて、ACTAやTPPなどの条例関係で議論されている「著作権侵害の非親告罪化」に関連するものです。現在の著作権侵害罪は親告罪なので、権利者が告訴しないと起訴されることはありません。また、運用上の話ですが、通常は権利者が被害届を出さないと警察は動きません。
これが非親告罪化されると、第三者(「告発厨」)が告発したり、警察機関が独自に捜査して起訴まで持って行くことが可能になってしまいます。現在の同人活動の多くは権利者の黙認の上に成り立っているわけですが、著作権法の非親告罪化により、このバランスが崩される可能性がでてきます。この辺の議論は福井健策先生の最新著作『ネットの自由vs著作権』で大変わかりやすく解説されていますので、興味ある方はご一読をおすすめします。
誤解5:コンテンツファイルをメール添付で送信すると違法にならないのでこの改正はザル法である。
これは、前述の文化庁のQ&AのQ6が最初言葉足らずだったことによる誤解と思われます。ダウンロードに関する規制は自動公衆送信された著作物だけが対象なので私信であるメールには関係ありません。しかし、メールの受け手は(私的使用目的である限り)違法ではないのですが、送信側のメールを添付する行為が複製権の侵害になり得ます。つまり、昔と同様に、アップ側は違法(刑事罰対象)、受け手側は(私的使用であれば)合法というのと同じです。文化庁Q&AのQ6が7月24付けで追記(以下の下線部分)されています(元々のQ6を見たときに「誤解する人が出そうなので直してもらうよう文化庁にコメント送ろうかな」と思ったのですがそうするまでもなく直りましたね。)
Q6. 友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたのですが、刑罰の対象になるのでしょうか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行うダウンロードが対象となります。著作権法上、「自動公衆送信」とは、公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと)のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。(ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。)
次回(明日)は改正の条文(119条3項)について分析します。