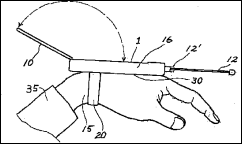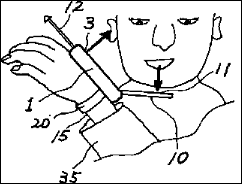本ブログの以前のエントリー(1, 2)ではダウンロード刑事罰化が制度的にどうなっているかという点についてできるだけ客観的に書いてきました。今回は、このような制度の何が問題なのかという点から私見を述べてみたいと思います(今頃言ってもしょうがないという話ではあるのですが)。
まず大前提として世の中は「けいさつはわるいことをしたやつはどんどんつかまえればよい」という仕組みでは動いていない点を念頭に置く必要があります。
刑罰(および、それに伴う逮捕・拘留等)は、個人の人権を大きく損なう可能性があります。ゆえに、刑罰は最後の手段として使うべきであり、違法行為なら何でも罰せばよいというものではありません。この刑事罰はできるだけ控えめに使うべきという考え方を「謙抑(けんよく)主義」と呼びます。謙抑主義は近代国家の刑法制度の基本です。
たとえば、米国著作権法における刑事罰の規定は以下のようになっています。
第506条 刑事犯罪
(a)著作権侵害罪
(1)総則-著作権を故意に侵害する者は、その侵害が以下の態様で行われる場合には、合衆国法典第18編第2319条の規定に従って処罰される。
(A)商業的利益または私的な経済的利得を目的とする行為、
(B)180日間に、1つ以上の著作権のある著作物について1部以上のコピーまたはレコード(その小売価格の総額が1000 ドルを超える場合に限る)を複製もしくは頒布(電子的手段によるものを含む)する行為、または
(C)商業的頒布を目的として作成中の著作物を、公衆がアクセス可能なコンピュータ・ネットワーク上に置いて利用可能にする方法によって頒布する行為(当該著作物が商業的頒布のために作成中の著作物であることを当該者が知りもしくは知るべきであった場合に限る)。(2)証拠-本項において、著作権のある著作物の複製または頒布の証拠は、それだけでは、故意侵害を立証するに十分ではないものとする。
(以下略)
ポイントは、1)非営利目的の複製(DL含む)は原則的に刑事罰の対象にはならない、2)少量のカジュアルコピーは刑事罰の対象とならない、3)制作中で発表前の作品を故意に公開するパターンは特別に刑事罰の対象(これは制作者の被害が甚大なのでしょうがないと思います)、4)複製・頒布をしているというだけで故意であると推定してはいけない、ということであります。結構、謙抑的だと思います。
日本においてダウンロード刑事罰化が推進された時の推進派の根拠のひとつとして「米国では既に違法DLも刑事罰化されている」というのがあったと思いますが、日本の刑罰規定の方が相当厳しいですね(ただし、米国では懲罰的賠償金とか法定賠償金等、民事の規定が結構厳しい点は考慮する必要はあります)。
「条文上は厳しいけど実際には悪質なケースしか逮捕されないからいいんじゃないか」という意見の方もいるかもしれないですが、形式上は犯罪だけど警察に大目に見てもらっている(恣意的にいつでも検挙できてしまう)という状況はあまりよろしくありません。
特に、アップロード行為は外界からの監視でわかりますので、十分な証拠を押さえた上で家宅捜索等ができます。ところがダウンロードはあくまでもプライベートな世界です。パケットを盗聴したり、ハニーポットサイトでも作らない限り、ダウンロード者の特定は難しいです。また、仮に何らかの形でログを見たところで、ストリーミング視聴しているのか、ダウンロードしているのかは区別しにくいです。「違法ダウンロードしている疑いがある」ということで家宅捜索されたのではたまりません。
先日、私が聞きにいった明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)セミナー「平成24年著作権法改正の評価と課題」 のパネルディスカッションにおいても、パネリストの先生は何度も「謙抑性」という論点を口にされていたと記憶しています。また、日弁連会長の声明でも「違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対」と述べられています。
特に、違法ダウンロード行為に対して刑罰を最後の手段として適用することが本当に必要なのかという議論が十分になされたとは言い難い点が問題です。文化庁の審議会では「刑事罰までは不要」という見解であったのを、会期末近くの国会でほとんど審議なしに土壇場で刑事罰が追加されているからです。先の日弁連会長の声明を引用すると、
インターネットの利用に関して刑事罰を科すという国民生活に重大な影響を及ぼす可能性がある法律改正が、国民的な議論がほとんどなされないまま、衆参両院において、わずか1週間足らずで審議されて可決されたということはあまりにも拙速であった。このように、今回の立法には手続的にも大きな問題があったと指摘 せざるを得ない。今後、このような形で私的領域における刑事罰の立法がなされることを、断じて許してはならない。
ということであります。
なお、違法ダウンロード刑事罰化は衆参ともほぼ全会一致で決まったのですが、民主党の森ゆうこ参院議員と川内博史衆院議員が最後まで反対の立場であったようです。ちなみに、推進派の中核としては自民の馳浩衆院議員がいます。有権者の方は選挙の際の参考にされるといいんじゃないかと思います。