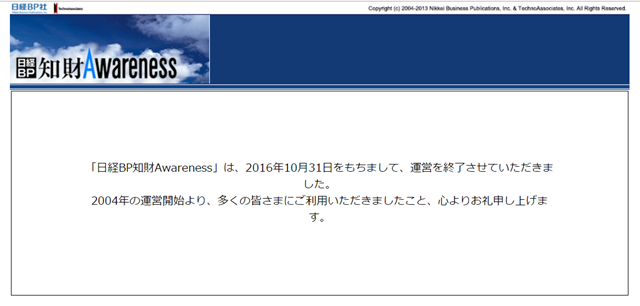ニューラルネット技術の採用により、Google翻訳が飛躍的に精度を向上させたことは周知かと思います(参考記事)。以前は、独語→英語のようなロマン語似た言語間の翻訳ならまだしも日本語への翻訳はちょっと厳しかったのですが、今や日本語と英語間でもかなり自然な翻訳が可能になっています(他の言語は読めないので検証できないですが、たぶ同様に精度が上がっているのでしょう)。
当然ながら、今までは非現実的だったGoogle翻訳による特許翻訳も十分検討に値するようになっています。
たとえば、適当に選んだ英語公報の一部を訳すと、こんな感じです。
In addition, the loading of an operating system (“OS”) refers to the initial placement of the operating system bootstrap loader. In one embodiment, during the OS load, a sector of information is typically loaded from a hard disk into the system memory. Alternatively, the bootstrap loader is loaded from a network into system memory. An OS “boot” refers to the execution of the bootstrap loader. This places the OS in control of the system. Some of the actions performed during the OS boot include system configuration, device detection, loading of drivers and user logins.
さらに、オペレーティングシステム(「OS」)のロードは、オペレーティングシステムブートストラップローダの初期配置を指す。一実施形態では、OSロード中に、情報のセクタが、通常、ハードディスクからシステムメモリにロードされる。あるいは、ブートストラップローダがネットワークからシステムメモリにロードされる。 OSのブートとは、ブートストラップローダの実行を指します。これにより、OSがシステムの制御下に置かれます。 OSの起動中に実行されるアクションには、システム構成、デバイス検出、ドライバのロード、ユーザーログインなどがあります。
十分読める日本語になっていると言えるでしょう。さらに言うと、”indexing 〜, identifying〜”という形式の方法クレームを訳すと、ちゃんと「〜索引付けするステップと、〜識別するステップと」と日本の請求項ぽく訳してくれるのでびっくりしました(原文にはどこにもstepなんて書いてないのに)。
ただ、上記の例文からもわかるように、である調とですます調が混在したり、用語の統一がなされなかったりするのでチェックは必要です。また、上記の文章ではないですが、なぜかFIG.1を図2と訳したり、否定文を肯定文で訳したりすることもあるのでさらに注意が必要です(構文解析をしないで機械学習だけでやってるのでこういうことになるのでしょう)。
自分の場合だと、英語→日本語で最終納品する場合は、Google様にやらせて自分で直すのと、最初から自分で直すのでは、そんなに時間が変わらないという感じでしょうか(一般に他人の訳文直すのは結構時間がかかります)。
PCT国内移行とか外国語出願のように後から誤訳訂正書を出せるケースで翻訳文提出の〆切が迫っている場合には便利かもしれません。米国出願のIDSにも使えるかもしれません。日本語が怪しげな海外の格安業者に任せるよりは全然ましでしょう。
さらに、自分は英語と日本語以外は読めないので、中国語とかスペイン語のOA等の中身をざっと理解する分には有用であると思いました。
しかし、ニューラルネット(ディープラーニング)の仕組みは一応理屈では分かっているのですが、どんな英文投げても瞬時にそれなりのクオリティで翻訳してくれる(しかも無料で)のは、何かコワイです。