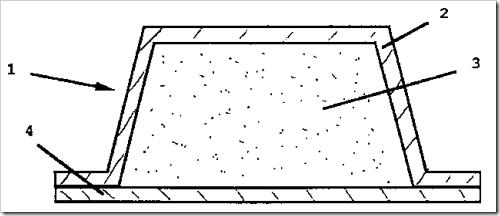「“iPad mini”の商標登録出願、米特許商標局に拒絶されていた」なんてニュースがいろいろな媒体に載っています。調べると、別に拒絶されたわけではなく、Office Actionが出ているだけです。Office Action(OA)とは、日本でいうと拒絶理由通知というものにあたり、このままだと拒絶になるので対応してくださいねという特許庁からの通知です。
商標に限らず特許でもそうですが、多くの国の審査制度では、いきなり拒絶にするということはなく、予告的な通知を行なって、出願人がしかるべき対応を行なえるようになっています。(ちなみに、中国の商標制度は通知なしでいきなり拒絶になるルールなのでちょっとやっかいです)。
ということで、「拒絶」というタイトルはミスリーディングだと思うのですが、日本国内の記事の元ネタになっているAFPの元記事のタイトルが、”US Patent Office denies ‘iPad Mini’ trademark”なのでそれに引っ張られたと思われます。
このiPad Miniに対するOAの内容は記述的商標にすぎないというものです(記述的商標については以前の記事で触れました)。「そのまんま」の商標ではないかというものです。これに対して、アップルのは使用による識別性(セカンダリーミーニング)があることを主張することになります(たぶんこの主張は認められるんじゃないかと思います)。(追記: OAをちゃんと読むと、iPadの部分はAppleが元から持っているiPad商標(富士通から買ったもの)を根拠に識別性を主張し、miniの部分は権利放棄すべしと書いてあるので商標全体として権利獲得するのは困難かもしれません。追記^2:ちなみに、iPhoneの商標登録出願があった時も最初は「iはインターネットを表わしてPhoneは電話だから”記述的商標”と考えられる」というOAは出ていたのですが、その後(Ciscoの先登録商標とのからみなどもあって)紆余曲折があった後に最終的には無事登録されています)。
また、提出した使用証拠(日本と違って米国の場合は商標を実際に使用しているこ)と、あるいは、使用する意図の宣誓が求められます)が不十分であるとの指摘もされているようですが、これは単に手続き上の瑕疵なので容易に補正可能です。
というわけで、これはわりと日常茶飯事の話であると言えます。
私も、(架空の)人名ぽい商標を米国に出願し、「この人の許可を取ったのか?」なんてOAをもらって「架空のキャラクターなので許可も糞もありません」(という主旨)の応答をして無事登録に至ったことがあります。