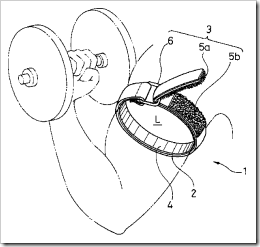言うまでもないですが、特許の対象となる発明は「自然法則を利用した技術的創作のうち高度なもの」と定義されていますので、自然法則を利用していないアイデアは特許の対象になりません。「ビジネスモデル特許」という言い方がありますが、日本ではビジネスモデル(ビジネスのやり方)それ自体は特許の対象外です。世の中で「ビジネスモデル特許」と言われているのは、実際には、ビジネスモデルを実現する情報システム(これは、コンピューターで動いてますので自然法則を利用していると言えます)の特許であることがほとんどです。
現実には、この「自然法則利用」要件のグレーゾーンもあります。一部に人為的判断が入っていても全体として自然法則を利用していれば特許の対象になりますし(もちろん、新規性・進歩性等の他の要件は別)、人のプロセスでコンピューターを使っていてもその使い方に何ら特徴がなく単に道具として使っているだけであれば、人為的取り決めにすぎないとされて特許の対象外になります、
さて、久しぶりに中山『特許法』を通読していたところ、この「自然法則を利用した」の要件のグレーゾーンの説明のところで、2つの知財高裁判例が上げられているのが目に止まりました(p99)。
ひとつめは「人間に自然に備えられた能力のうち、子音に対する識別能力が高いことに着目し、その性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせる」というアイデアが自然法則を利用したものであると判断された「対訳辞書事件」です。
もうひとつは、「数多くの対象となる言葉を、その意味する内容に則って、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の4つの思想にあてはめて、分類し、連ね並べて整理する」アイデアが自然法則を利用したものではない(単に人による分類作業)と判断された「宇宙論事件」です。この判決文は裁判所サイトで読めます。特許の公開番号は特開2005-037867です(IPDLは直リンできないのでご興味ある方は自分でサーチしてください)。なお、要約は以下のようになっています。
【要約】
【課題】 宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の各思想を、記号等を用いてコンパクトに理論化を可能とする。
【解決手段】 記号化した対語だけを用い、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の各思想を基に、自然科学、社会科学、人文科学の定説で根拠付け、その記号化した対語を羅列する事で、限定的に、そしてコンパクトに理論化を可能とする。
この手の「特殊特許」の公報はネタとしてよく取り上げられますが、裁判まで行ったのは珍しいような気がします(特許庁の審決を取り消す訴訟なので地裁をパスしていきなり知財高裁で争われます(なお、原告は本人代理))。判決文を読むと、原告はかなり「独自性」の高い主張を展開しており、これにちゃんと論理立ててまじめに対応している裁判官や特許側代理人側の気持ちを考えるとちょっと胸熱です。
中山先生が何でこんな「特殊特許」を判例として引用したか(まさか、ネタとしてではないでしょう)ですが、自然法則の利用性について知財高裁が判断を示した比較的最近の判例なのと、「対訳辞書事件」との対比で、自然法則利用性の判断の境界がクリアーになるという点が重要であったのだと思います。
今後、法研究の世界でこの「宇宙論事件」が取り上げられる可能性もあるのかと思うと、これまた胸熱です。(追記:今、仕事場に来て『注解特許法』を見たら普通に載ってました。)