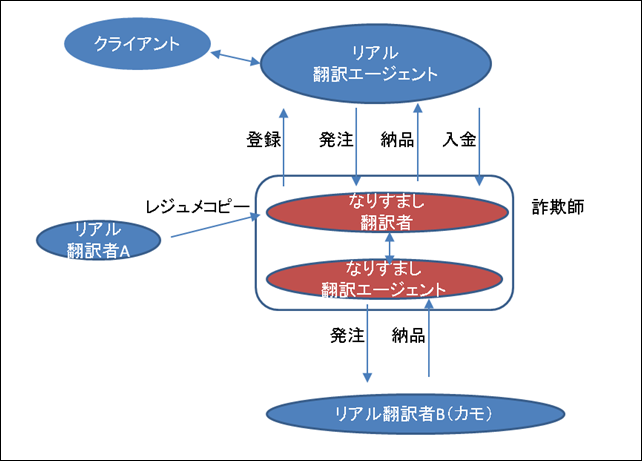今、シリコンバレーのNetApp本社で開催されているアナリストイベントに来ています。
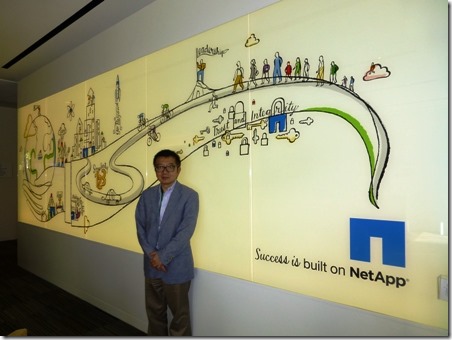

以降、何回かにわけてNDAに違反しない範囲で同社の戦略のポイントを分析していこうと思います。ストレージというと地味な印象もありますが、実は非常にエキサイティングな分野のひとつであります。そう言えば、ちょっと前にPublickeyの新野さんと立ち話した時に「今、エンタープライズIT分野でおもしろい分野はどこでしょうかね?」という質問に「ストレージですかねえ」なんて答が帰ってきたりしましたね。
さて、NetAppが挙げるストレージの重要トレンドは以下のとおりです。
- フラッシュ
- SDDC(Software Defined Data Center)
- クラウド
- コンバージド・インフラストラクチャ
- モバイル
- ビッグデータ
です。特に、クラウドにおける同社の戦略には興味深いものがありました。戦略の内容そのものについて触れる前に、一般的にエンタープライズにおけるクラウドの計画でストレージがきわめて重要である理由について述べておきましょう。
簡単に言えばコンピューティングの移動は簡単だがデータの移動では簡単ではないということです。
たとえば、クラウド上でHadoopを使って2TB のデータを1分で処理できるソリューションがあったとします。これを使ってオンプレミスのシステムをオフロードできるかもしれないと思っても、分析対象のデータがオンプレミスにあったとすれば、クラウドへの2TBデータの移動だけで半日以上かかってしまいます。データの処理が1分でできてもあまり意味はないですね。世界中どこでも処理ができるのがクラウドのポイントですが、大量データが絡むと現実的にはそういうわけにはいきません。
結局、データそのものをクラウドに置くか、それともオンプレミスとクラウドの両方に置くか(この場合両者の同期をどう取るかという新たな課題が生じます)、さらには、Hadoopの処理をクラウドでやるのはあきらめてオンプレミスでやるか(サーバの調達の問題が生じます)、等々の代替案を入念に検討する必要があります。
つまり(大容量のデータを使わない科学技術計算等をのぞき)エンタープライズのクラウドの全体設計においてはデータの配置がきわめて重要であり、その結果として、データの入れ物であるストレージでどのようなソリューションを使うかということが、重要な意思決定要素になることになるというわけです。
この領域で、NetAppが具体的にどのようなソリューションを提供しているかについては次回に書きます。