特許情報検索サイトJ-PlatPat(旧IPDL)の商標検索メニュー、今まで「音」、「色彩のみ」、「動き」等々のチェックボックスが画面上にはあったものの機能していませんでしたが、ようやく実装されたようです(音商標については5月26日から対応)。
タイプ別のチェックだけして他に情報を入力しないで検索すると現時点で出願公開済あるいは登録済みの新しいタイプの商標を一括表示できます。ながめていると、あの会社があの色を(あの音)を、というのが数多くあって興味深いです。本当に使用による識別性はあるのだろうかとの疑義を感じるものもありますが、これは特許庁の審査官が需要者の立場で決める話なので、ここで勝手にコメントするのはやめておきます。
残念なのは、J-PlatPatが相変わらず固定リンク機能を提供していない点です(URLをWebページに貼ってもそれはそのセッションでのみ一時的なリンクで他人からは見られません)。せっかく興味深い商標登録出願を見つけても、出願番号を書いて検索して下さいとするか、画面コピーを貼るかしかありません。
とは言え、twitterで商標公開公報を自動フィードしているアカウントの商標速報botが、新しいタイプの商標にも対応しましたので、そのツイートを使うことでWebやブログ上で当該商標公開公報を容易に公開できます。音商標ならSoundcloud経由で音を聞き、動き商標であれば願書ではイメージの組み合わせで表記されている動きを動画として見ることができます(商標速報botの中の人に深く感謝したいです)。
たとえば、円谷プロによるこの「動き商標」の出願はなかなか興味深いですね(オッサン限定ですが)。
[商願2015-29857] 商標:[画像7枚] (動き商標) / 出願人:株式会社円谷プロダクション / 出願日:2015年4月1日 / 区分:9(業務用テレビゲーム機用プログラムほか),28(キャラクターを模したおもちゃほか)… pic.twitter.com/yaHflrL88p
— 商標速報bot (高速モード) (@trademark_bot) 2015, 4月 19


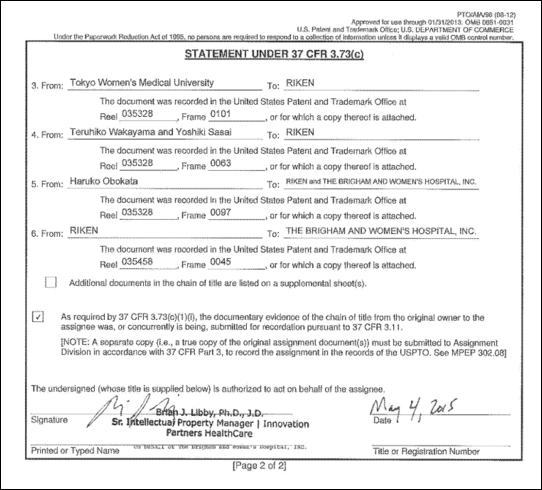

 D727,787
D727,787
 D727,197
D727,197 D727,198
D727,198







