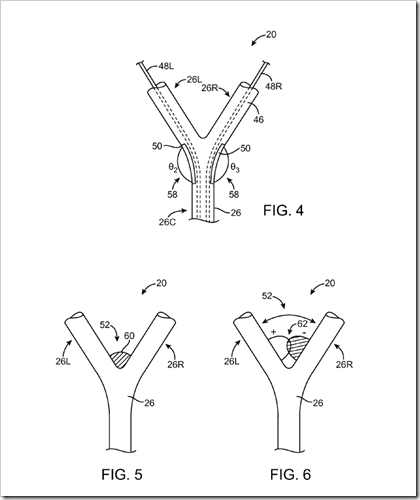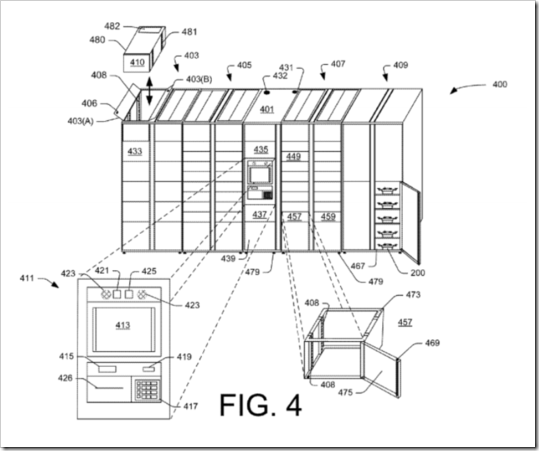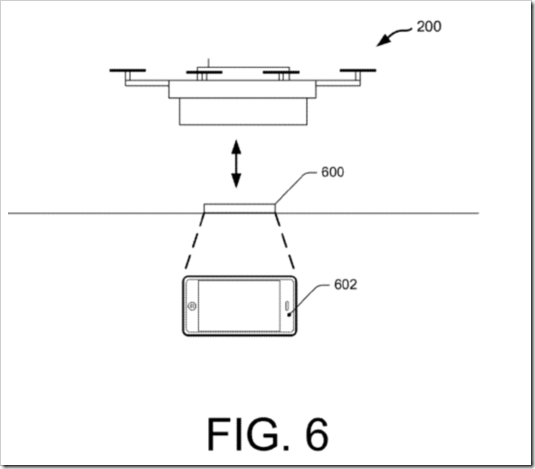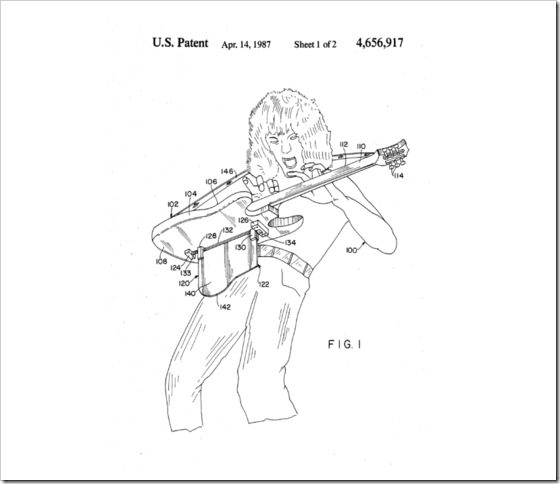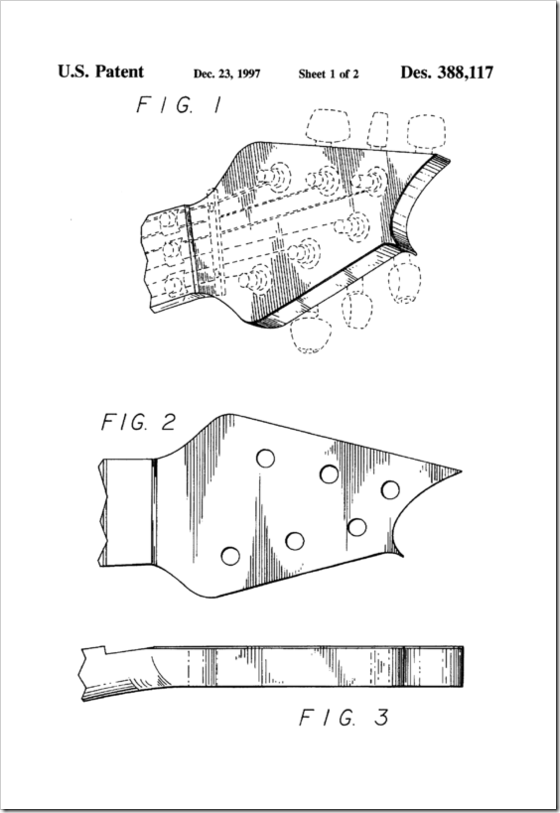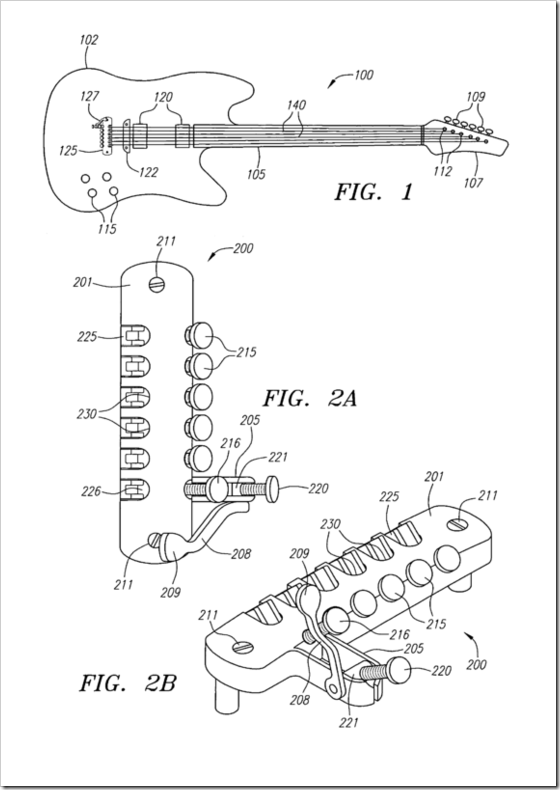ある大御所ロック歌手が昔の持ち歌をことわりなくカバーされたことに苦言を呈してちょっと揉めたという事件がありました。もともと法律的な話でもなんでもなく、業界の礼儀的な話であるので、この事件についてはここでは論じません。元々の事件についてコメントされたい方は関連Togetterをサーチしてコメントするなどしてください。
ここで論じたいのは、自分の持ち歌を不本意にカバーされた歌手は著作権法上何かできるのかということです。上記の事件について、俺様著作権論を展開している人が見受けられたのでここで整理しておきましょうということです。
まず、大前提として、著作権法上は歌唱は著作物ではありません。歌唱は実演です。そして、実演は著作物とは別物で関連する権利も違います。なお、旧著作権法(明治32年)では歌唱も著作物のひとつとされていました。なので、歌唱は著作物であると決めてもよいのですが、今はそうなってないということです。
著作者(著作権者)と実演家(歌手等)がごっちゃになってる人がたまに見受けられます。
たとえば、JASRACに対する都市伝説的批判において、ライブハウスから徴収した金額はAKB48のようなメジャーなアーティストにしか回らないなんて話を聞くことがあります(JASRACの使用料分配に関する話はまた別途)。しかし、AKB48の曲がカラオケで歌われたり、ライブハウスでカバー演奏されたりしたことで、JASRACに入った著作権使用料はAKB48メンバーには回りません。回るのは秋元康等、楽曲の作詞家・作曲家に対してです(もちろん、メンバー自身が作詞・作曲した曲の場合を除きます)。
これに関連して余談ですが、作詞・作曲もするメンバーと実演のみのメンバーがいるバンドがヒット曲を出すと(後者には著作権収入が入らないことから)メンバー間で大きな収入格差が生じてバンドの不和の一因になるというケースもあるようです。
さて、本題のカバー曲を出されたことに対して実演家は何ができるかについて考えます。簡単に言えば、著作権法上は楽曲は著作者(作曲家・作詞家)のものであって、歌手(実演家)のものではないので、楽曲がどう使われるかを歌手はコントロールできません。
もちろん、実演家にも(著作権とは別の)権利があります。
第一に、著作隣接権(実演家の権利)です。この権利には録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、商業用レコードの貸与権があります。著作者の権利とは異なり複製権や翻案権がありませんので、仮に、カバーにおいてオリジナルの歌唱の物真似やインスパイア的な要素があったとしても、実演家の著作隣接権の侵害にはなり得ません。
なお、実務上は、歌手やバンドの著作隣接権はレコード会社との専属録音契約によってレコード会社に譲渡されていることが通常です(それがいやなら自費出版すればよいので、あながちひどい話ではありません。)
もうひとつの実演家の権利として実演家人格権があります。実演家人格権には氏名表示権と同一性保持権があります。同一性保持権(90条の3)は「(実演家が)自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けない」権利です。「自己の実演の改変」の話をしていますので、カバー曲(他人による別の実演)は関係ありません。ちなみに、実演家の同一性保持権を侵害するケースとしては、ライブでミスがあったシーンだけをまとめて映像作品にされてしまったというようなケースが考えられるのではないかと思います。
繰り返しますが、ここでは著作権法的に歌手(実演家)にどういう権利があるかを論じているだけなので、業界の儀礼的な話はまた別です。私見ですが、カバー曲をライブでやるだけでなくCDを出し、かつ、その曲とオリジナルの歌手の結びつきがきわめて強いという認識があるのであれば、許諾というほど大げさなものではなくてもひと言おことわりしておくべきだと思います(そして、それは事務所等の裏方さんがちゃんとやっておくべき仕事だと思います)。