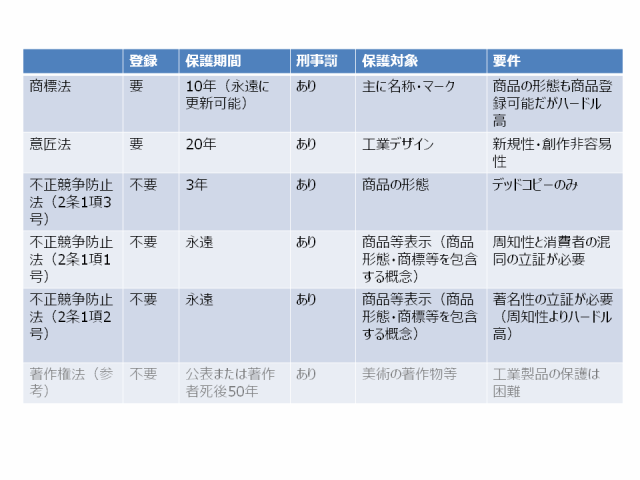たまに聞かれる偽ブランド品販売で逮捕というニュースでは、商標法違反容疑のケースがほとんどです。しかし、偽物の販売を防止できるのは商標法だけでありません。
先日報道された「衣料販売会社社長ら逮捕=人気ブランド模倣の疑い—大阪府警」という事件では、人気ブランドのデザインを模倣した服を販売していた会社の社長らが不正競争防止法違反(商品形態模倣行為)容疑で大阪府警に逮捕されました。このGRL(グレイル)という会社、楽天等にも出店し、有名タレントを使って宣伝していた結構有名所で、社長は再三の警告を無視していたそうですが、商標登録されていない、あるいは、類似商標(ブランド名やマーク)を使用していないから大丈夫と高をくくっていたのでしょうか?
不正競争防止法「商品形態模倣行為」とは以下の規定です。元々は刑事罰対象では無かったのですが、平成17年の改正で刑事罰が付加されました。
不正競争防止法2条1項3号 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
そもそも商標権は事前の出願・登録が必要です。また、基本的には名称やマークに対する保護です。商品形態そのものを商標にできるケースもありますが、消費者の間で相当の周知性を獲得していないと登録のハードルは高いです。そうなると、それほど周知でもなく、ライフサイクルもせいぜい数年という通常のファッション商品を商標権で保護するのはあまり現実的ではありません。しかし、この場合でも不正競争防止法の上記規定で刑事罰も含めて偽ブランド販売を防ぐことが可能です。
なお、2条1項3号の規定は販売から3年以内に限定されます(19条1項5号イで適用除外されています)。また、基本的にデッドコピー品でないと適用されません。なので、あくまでも商標法や意匠法を補完する制度と考えた方がよいでしょう。実際には、この規定が適用されて立件されることはあまりなく、別記事によれば、この規定により当事者が逮捕されたのは今回が初めてだそうです。
ということで、ライフサイクルの長い商品を長期的に保護をしたいのであれば、やはり商標登録や意匠登録をしておくことが適切です。また、周知性が高い商品であれば、不正競争防止法の1条1項1号や2号で権利行使することも可能です。
ちょっとややこしいので以下に偽物ファッション商品を防ぐための法律ごとの特性を簡単にまとめます。ファッション商品の文脈で書いてますが、他の商品(たとえば、ガジェット類)にも適用される話です。また、著作権については、一般的には大量生産の工業製品には適用されない(キャラクターの絵でも描いてあれば別ですが、それは絵に対する保護であって工業製品に対する保護ではありません)とされていたのですが、最近、裁判において家具のデザインの著作物性を肯定する判断がされた(参照過去記事)ので、念のため付記しておきました。
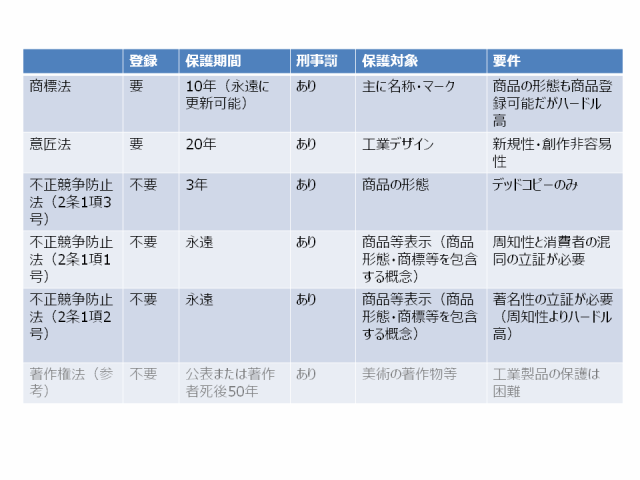
[AD]商標法、意匠法、不正競争防止法に関するご相談はこちらから。