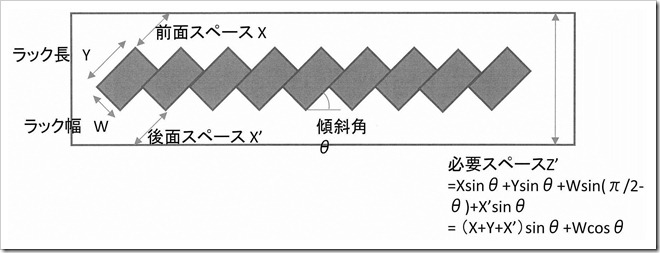#できるだけ簡潔にまとめようと思ったのですがやはり長くなってしまいました。お急ぎの方は下の「まとめのまとめ」を先に見てください。
本当に直前になってしまいましたが、前回に引き続き、いよいよ10/1から施行の著作権法改正の最重要ポイントとなる違法ダウンロード刑事罰化に関して実際の条文を見て検討していくことにしましょう(なお、他の改正事項、特にDVDリッピング違法化については後日書きます)。
違法ダウンロード刑事罰化に直接関係する著作権法の条文は今回新設された119条第3項です。
第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
いきなり読んでもわかりにくいので構成要素に分解して見ていきましょう。法律の条文の多くは要件→効果、つまり、条件Aを満足するとBという効果になるというIF〜THEN文のような構造になっています。
先に、THEN節にあたる効果の方を見ていきましょう。119条3項で効果にあたるのは「2年以下の懲役 and/or 200万円以下の罰金」です。これは、通常の著作権侵害罪(10年以下の懲役 and/or 1000万円以下の罰金)よりもちょっと軽くなってます(とは言っても、一般市民にとっては警察に逮捕されること自身が社会的に大ダメージなので刑罰の重さはあんまり関係ないですよね)。
次に、ややこしいですが、要件(条件)の方をひとつひとつ見ていきましょう。
1. 第30条第1項に定める私的使用の目的をもって
そもそも私的使用目的でなければ(たとえば、他人に公開するためにダウンロードした場合など)は、普通の著作権侵害(刑事罰が重い方)として扱われます(ダウンロード違法化・刑事罰化を議論するまでもなく元から違法・刑事罰の対象)ので、この条文で扱うのは私的使用目的ダウンロードに限定すると言っています。
2. 有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)
ここはカッコ書きで「有償著作物等」の定義をしていますので先に説明しておきます。
2-a. 録音され、又は録画された著作物又は実演等
対象は音又は映像コンテンツに限られることを言ってます。プログラムの著作物や文書の著作物、マンガなどは対象外です。
2-b.(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)
パブリックドメインのものは対象にしないことを言っています。「有償」という縛りが入っているのでわざわざ言うまでもないと思うのですが、著作権切れの格安DVDなどパブリックドメインだけど有償というケースはないことはないので、それはダウンロード違法化の対象外になることを明記しています。
2-c. 有償で公衆に提供され、又は提示されているもの
普通に店で売っているCDやDVDのコンテンツが対象になることは明らかですが。結構グレーゾーンがありそうな要件です。文化庁Q&A(PDF)のQ6では、「ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません」と言っていますが、現実には判断は難しいでしょう。
2-d.(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)有償で売っている著作物であってもそもそも売ること自体が著作権を侵害している場合、要するに、海賊版(市販CDのそのままコピーしたものという意味ではなくて、たとえば、未発表ライブ音源を勝手にCD化したブートレッグ盤という意味です)の場合には対象外というということだと思います。もちろん、ブート盤を作ったこと自体は別途著作権侵害に問われます。
3. (有償著作物等の)著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信
言うまでもなく、アップロード行為が権利侵害行為であることがダウンロード行為が刑事罰の対象となる前提です。私信メールでの送信は自動公衆送信ではないのでこの条文の対象外であるのは前回書いたとおりです。
4. 自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)
前記の「自動公衆送信」はサーバが海外にあった場合でも刑事罰の対象にすると言っています。サーバが海外にあるとアップロード者を捜査しようと思っても実際には難しいわけですが、その場合に国内のダウンロード者だけを捜査できるよということです(まさに、これが刑事罰化の目的のひとつだと思っています)。
5.デジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて
「その事実を知りながら」つまり「違法にアップされたことを知りながら」ということです。これを実際どう判断するかは難しいところです。少なくとも警告があっても無視してダウンロードを続けていれば「その事実を知りながら」ということになるでしょう。文化庁Q&Aでは「警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます」と他人事のような書き方をしています。ただし、現実には違法アップロードの場合等で警告なしにいきなり警察が家宅捜索に来て逮捕みたいなケースもあるようです。
6.著作権又は著作隣接権を侵害した
権利者が許諾したような場合は対象外にするということだと思います(市販CDやDVDの場合には現実的にあり得ないと思いますが)。
これに加えて、一昨年の改正(ダウンロード違法化)に関する30条1項3号
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
も含めて、ダウンロード行為が刑事罰対象、違法だけど刑事罰対象でない、合法と分かれることになります。ややこしいですね。
まとめのまとめ
条件をできるだけ簡略化してまとめると以下のようになります。
| 違法アップ | デジタル方式の録音・録画 | 有償著作物 | 事実を知りながら |
| 刑事罰対象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 違法(刑事罰なし) | ○ | ○ | ー | ○ |
具体的なパターンで見ていきましょう。
- 市販のCDやDVDのコンテンツが違法にアップされたサイトからそれを知ってダウンロードする行為 → 刑事罰対象です(まさに今回の改正がメインターゲットにしている行為だと思われます)
- 市販のCDやDVDのコンテンツが違法にアップされた海外サイトからそれを知ってダウンロードする行為 → 刑事罰対象です(サーバが海外でも同上です)
- TV番組が違法にアップされたサイト(海外含む)からそれを知ってダウンロードする行為 → 違法ですが有償著作物ではないので刑事罰対象ではありません(ただし、そのTV番組がDVD化されている時には刑事罰の対象になります)
- マンガや書籍スキャンが違法にアップされたサイト(海外含む)からそれを知ってダウンロードする行為 → 録音・録画ではないので違法ではありません(倫理的な問題は別)
- YouTubeに権利者がアップした公式PVをツールを使ってダウンロードする行為 → 違法にアップされたコンテンツではないので違法ではありません(ただし、YouTubeの利用規約違反です)
なお、念のために書いておくと、上記はあくまで私的使用を前提にした話なので、ダウンロードしたコンテンツを他人に提供したりすると(DL違法化とは関係なしに)著作権侵害(故意ならば刑事罰対象)となります。
他にもどう扱われるのか知りたいパターンがありましたら、コメント欄に書いていただければ可能な限りお答えしたいと思います。