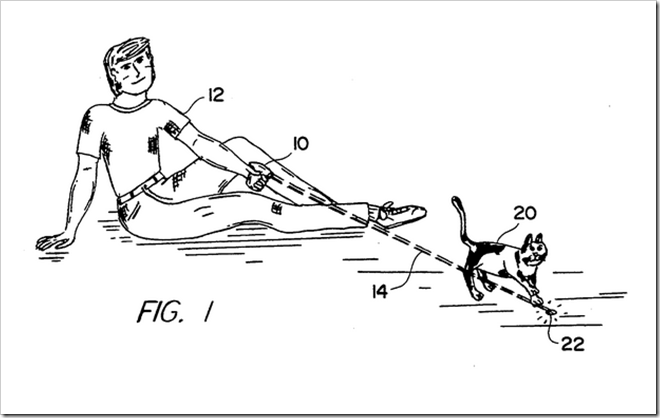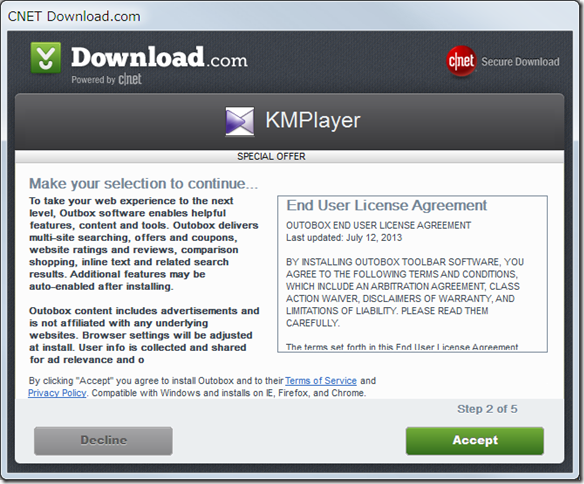先日、弊所のクライアントから「何か商標の件で英語のメールが来てるんだけど」と相談がありました。そのクライアントの了承を得て、名前を隠した上でメールの内容を書くと以下のとおりです。
Dear CEO or Director,
We are a senior domain registrar in Hong Kong.
_1.On Dec.17__, 2013, we received an application formally. One company named Lanxia Investment Co. wanted to register the Network Marketing Keyword “xxxxxxxxxxx” with some related domain names with our organization.
2. During our preliminary investigation, we found that these Domain Names’ keyword is identical with your Trade Mark, this is why we inform you._
3. I wonder whether did you consigned Lanxia Investment Co. to register these Domain Names with us? _
Currently, we have already postponed this company’s application. Pls let the relevant principal make a confirmation with me ASAP.
Thanks & Regards,
Alice Liu
____*__Hong Kong__ *
*Mail: aliu@hkcreating.com
<mailto:aliu@hkcreating.com>*mailto:aliu@hkbweb.hk**
**
*Internet: www.hkcreating.hk <http://www.hkcreating.hk/>*
要は「香港のレジストラーだけど貴社の登録商標と類似のドメイン名を登録しようとしている会社がいるので手続きをいったん止めている、このまま登録してしまってよいか至急連絡されたい」ということです。
一瞬、私が代理で問い合わせようかと思いましたが、いろいろ怪しい点があります。
1) このクライアントの商標登録はカタカナであり、わざわざ香港の業者が日本のカタカナ登録商標を調べるとは思えない。
2) ドメイン名が商標権に抵触しそうなので登録を保留する運用をするレジストラーなんて聞いたことがない。
3) リンクが貼ってあるhkcreating.hkというWebサイトは正規のレジストラーのように見えるが、メールの返信先はhkweb.hkという別のドメイン
ということで調べてみると、やっぱり詐欺でした。このメールと同様の文面が送られた事例がいろんなところに載っています。これに返信すると「先方はどうしてもこのドメインを取りたいと言っている、それを防ぐには貴社が登録するしかない、弊社に頼めば格安のxx万円で登録しますよ」と法外な料金を請求するという仕組みのようです(ひょっとすると登録した振りで金だけ取られるのかもしれません)。
たぶん、たとえばfoobar.jpというドメインがあったとすれば「あなたの登録商標foobarを登録しようとしている企業があるが(略」というメールをinfo@ foobar.jpに対して自動的に送るボットがあるのでしょう。当然、登録商標なんてチェックしてなくて、社名=ドメイン名=登録商標という企業は多いので、そのうちのごく一部がひっかかることを狙っているのでしょう。
わりと有名な話のようですがご注意下さい。
これとは全然別に、ドメイン名について英語の警告メールが届いたけど中味がよくわからないという相談を受けたこともありました。米国企業の顧問法律事務所が発信人で「貴社のドメインがxxx社(超大手)の登録商標と類似なので放棄してほしい。放棄しないと法的措置を取る」みたいな内容でした。
こちらは、メールアドレスがちゃんとした法律事務所のものですし、内容的にも詐欺とは思えなかったのでちゃんと対応することにしました。この登録商標は日本では普通名称化しているような気もしたのですが、ドメイン主は特にそのドメインにこだわってないようだったので「不正目的で取得したわけではないので放棄する義務はないと思うが、ドメイン取得料金と名刺印刷代の実費を払ってくれれば放棄しますよ」旨のメールを返して双方納得の上で和解しました。後でちゃんとお金も振り込んでもらえたようです。