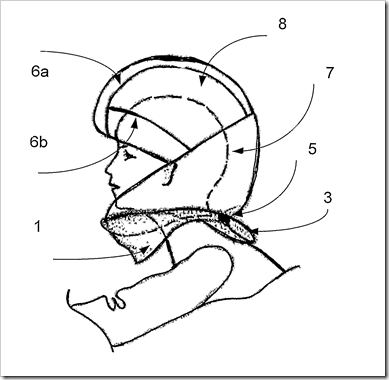昨日のエントリーの続きです。
昨日のエントリーの追記でも書きましたが、DMM電子書籍ViewerにはCypherGuardという画面キャプチャー防止のソフトウェアが含まれているようです。DMM電子書籍Viewerで電子書籍閲覧中にWindowsのPrint Screenキーを押すと警告ダイアログが出て画面キャプチャーできません。また、Windowsの画面キャプチャーツールであるSnipping Toolを立ち上げると、立ち上げた時点で画面全体がCypherGuardのロゴで埋められ書籍の画面キャプチャーはできなくなります。Snipping Toolの実行ファイル名を変えても同じなので、たぶんWindowsのAPIをフックしているのでしょう。
コミスケ3にはこの画面キャプチャー防止機能を回避する機能が含まれていたようです。正直、反社会的行為ですし、このようなソフトウェアを販売したことによる民事上の責任はあると思いますが、警察に逮捕されるか(刑事罰に相当するか)はまた別の話です。
刑事罰に相当するためには法文上の明確な根拠が必要です(罪刑法定主義)。「画面キャプチャー防止という保護手段を回避しているじゃないか」と一般用語で解釈してはダメであり、著作権法上の定義に合致しているかを検討する必要があります。
著作権法では「技術的保護手段」を以下のように定義しています。CypherGuardの画面キャプチャ防止機能がこの定義に当てはまるかどうかを検討してみましょう。
著作権法2条1項20号 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
要件に分けて考えてみると、技術的保護手段と言えるためには、大きく以下が必要です。
1)電磁的方法による保護であること
2)著作権等の侵害の防止・抑止をする手段であること
3)-A 著作物の利用に用いられる機器が特定の反応をする信号を音・影像とともに記録、もしくは送信していること
または
3)-B 著作物の利用に用いられる機器が特定の変換を必要とするよう音・影像を変換して記録媒体に記録、もしくは送信していること
===
1)と2)の要件については検討するまでもなく当てはまるでしょう。要は、3)-Aあるいは3)-Bの要件に当てはまるかがポイントです。なお、書籍は想定されていないように思えますが、電子書籍にはマンガもありますので影像と解釈するのは問題ないでしょう。
3)-Aは、SCMS、CGMS、マクロビジョン等のように、コピー等する側の機器がコピープロテクト信号を検知してコピー等を行なわせない仕組みです(従って機器がプロテクト信号に無反応だとコピーできてしまいます)。3)-Bは、DVDのCCSのようにコピーはできてしまうが、そのままでは暗号化されていて見られないようにする仕組みです。
CypherGuardソフト+Windowsのディスプレイドライバ+物理的なディスプレイを「機器」と考えて、CypherGuardが特定の反応をする(この場合は画面キャプチャを禁止する)「信号」をDMM電子書籍Viewerが「送信」していると解釈すれば、3)-Aの要件に当てはまると言えなくもないかもかもしれません(ちょっと苦しい?)。
なお、DMM電子書籍Viewerの内部動作によりますが、3)-Bの要件に当てはまるような仕組みになっていることはちょっと想定しがたいかと思います。
まあ、本件については今後の成り行きを見守りたいと思います。なお、私の立場としては別にコミスケ3のメーカーを擁護しているわけではなく、根拠なしに刑事罰の対象になっては困るので、そういう根拠が本当にあるのかなという点に興味があるだけです。