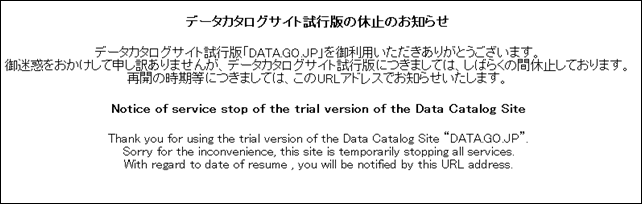「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板(2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。
また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。
「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。
2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約束事があったのかはわかりませんが、一般論として、このようなケース(周知商標の使用者ではない人が先に商標登録出願を行なってしまった場合)に商標法としてどう扱われるかについて検討します。
日本の商標法の大原則は先願主義、つまり、先に出願した人が優先しますが、それでも未登録周知商標については保護される規定があります(「2ch」は微妙かもしれませんが、「2ちゃんねる」が周知商標であるとの主張は十分成り立つと思います)。
まず、商標が商標登録されない条件のひとつとして、以下があります(第4条1項10号)。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
「2ch」、および、「2ちゃんねる」はこの条件に合致する可能性があります。特許庁の出願審査経過を見ると「2ch」は出願されたばかりでまだ何も行なわれていませんが、「2ちゃんねる」は一度拒絶理由通知が出ています(おそらく、上記の4条1項10号だと思います)。
また、仮に登録されてしまった場合でも、異議申立、および、無効審判によって、再度、商標登録の有効性を争うことも可能です。
さらに、先使用権と呼ばれる規定もあります(32条)。
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(中略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
これは、先に使用して周知になっていれば、その後で他人が商標登録してもその商標権に対して対抗できるということです。このケースでいうと、仮にひろゆき氏が「2ちゃんねる」の商標登録に成功しても、ジム・ワトキンス氏に対しては権利行使できない(他の人に対してはできる)可能性があることを意味します。まあ、先使用権が認められるかどうかは、両者の間の個別事情(たとえば、業務の承継がちゃんと行なわれているのか等)も関係してきますので何とも言えませんが。