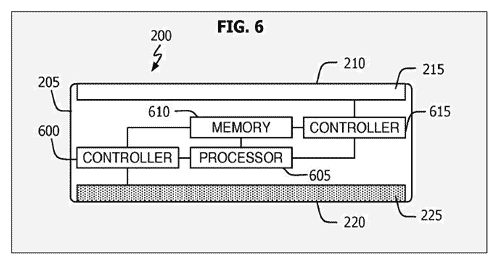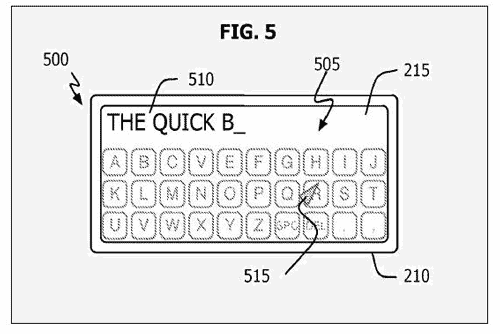2010年1月1日より施行予定の著作権法改正に関する解説が文化庁のサイトに載っています。関心のある方は是非ご一読をお勧めします。
やはり最も興味深いポイントは「ダウンロード違法化」だと思いますが、これに関して、以下のようなQ&Aが載っています(下線は原文ママ、太字は栗原による)。
問11
違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(第30条1項3号)答
インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模となっている状 況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないということを広報し,違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です。
もし,違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で,支払の請求がいきなり送りつけられた場合は,悪徳事業者による架空請求詐欺(振り込め詐欺) である疑いがありますので,文化庁著作権課や関係する権利者団体の相談窓口に問い合わせるなど内容をよく確認し,すぐに現金を支払うことのないようご注意 ください。
下線部の表現は「基本的に」、「予定です」等となっていることから絶対にこのような運用が行なわれるという保証はないわけですが、これが文化庁の公式ページにある情報であることを考えると、「ダウンロード違法化」の規定はできるだけ警告規定に留めたいという意思が感じられると思います(当ブログの過去エントリー「違法ダウンロードが社会正義に反しないとはどういうことか」も参照下さい)。
ところで、上記引用の太字部分(「あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難」)は結構重要だと思います。証拠調べという観点から言うとアップロード(より正確には送信可能化)とダウンロードはかなり違います。送信可能化行為については、ネット経由で著作物がダウンロード可能になっていることを(権利者の合意の元に)試してみればすぐに証拠がつかめます(実際、違法アップロード者の検挙はこういうプロセスになっているはずです)。その一方で、ダウンロード行為の証拠をつかむには、通信路の盗聴、ハニーポット、パソコンの押収等が必要となるでしょう。警察が行なうことすら難しい行為なので、民事の枠組みでこれらが正当化されることはないと思います。他に考えられる可能性としては、違法アップロード者のパソコンが押収されてダウンロード・ログが明らかになるケースくらいでしょうか?
著作権法の解釈におけるダウンロードが「私的目的複製」というのは屁理屈のように思われるかもしれませんが、こういう視点で見ると、送信可能化(アップロード)行為とは異なり、かなり「私的」な要素が強いです。そもそも、どの教科書を見ても著作権法において「私的目的複製」が許される理由として、(現実的に見て)権利侵害のチェックが困難という点が挙げられています。ダウンロードについてもこれは当てはまるでしょう(ただし、P2Pからのダウンロードはダウンロード即送信可能化となり得るので別論)。
なお、MIAUが「ダウンロード違法化」に反対していたにもかかわらず法律改正が成立してしまったことについて「MIAUの努力は無駄だった」という主張をする人もいるかもしれませんが私はそうは思いません。MIAUが一定のポジションを取ってくれたおかげで「ダウンロード違法化」の規定が警告規定に留まったとも考えられます。「MIAUが反対しなくても今のような形に決まっていた」という主張もあるかもしれませんが、今となっては結果論だと思います。
もちろん、実質上の警告規定に留まっているからといって違法ダウンロードを「その事実を知りながら」行なう行為をやって良いということではありません。法の意思を尊重した行動が求められるのは当然です。不正競争防止法上刑事罰がないからと言って、サイバースクワッティング行為をどんどんやって良いというわけではないのと同じです。