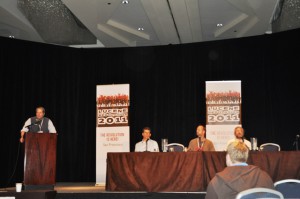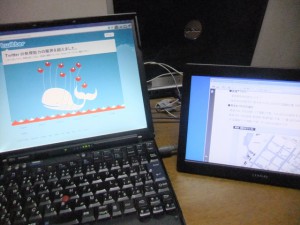仕事場やプライベートの部屋がちらかる最大の要因と言えばやはり書類でしょう。自分は、ScanSnapと裁断機を買って、原本が必須なものを除いたすべての書類や雑誌類を電子化するようにしてから部屋がだいぶ片付くようになりました。言うまでもないですが、CDもリップしてオリジナルを別の場所にしまっておくことでかなりスペースが節約できます。
部屋をすっきりさせる上でのもうひとつの障害にケーブリングがあります。当然ながらLANは無線化することですっきりしますが、USB系のデバイスは困ってしまいます。私もScanSnapに加えて、Brotherの住所ラベルプリンタとCASIOのネームランドのプリンタをUSB接続して常用してますが、できれば机の上は空けておきたいのでこれらのUSB機器は遠くに置きたいです。ところが、USBケーブルは仕様上は5mまでしか延ばせませんし、LANケーブルに比較して太めなので取り回しに困ってしまいます。
ということで、I-O DataのETG-DS/US-HSという型番のUSBデバイスサーバという製品を買ってみました。LANを経由してUSB系のデバイスを接続するための製品です(なお、各パソコンに専用クライアントソフトが必要です)。他にも同種の製品がありますが外見が似てるのでOEM元はひとつなのかもしれません。
ケーブリングがすっきりする以外に、この種の製品が提供するもうひとつのメリットとしてひとつのUSB機器を複数のパソコンから切り替えて使えるということがあります。当然ですが、プリンタ系以外のデバイスのほとんどは一時点でひとつのパソコンからしか使えませんから、あるパソコンで接続を開放して、別のパソコンで接続するという操作が必要になります(それでもケーブル抜き差しするよりは全然楽です)。
ScanSnapと上記のプリンタ系デバイスは快調に動作しています。細いLANケーブルを壁際に這わせて3つのUSB機器をつなげますのでかなり配線がすっきりしました。USBデバイスでもリアルタイム性が重要なワンセグチューナーだとかオーディオ系はダメです。ネットのレビューで、USBのHDDをつないでどーしたこーしたと書いてあるものがありましたが、HDD共用は素直にNASを使うべきではと思います。
なお、さらにLANを無線化したらどうなるかと思いバッファローのイーサネットコンバータを使ってみましたが、ScanSnapの反応が明らかに悪くなったのでやめました。無線化したところでどっちにしろ電源ケーブルは必要なのでまあ有線でもしょうがないかなと思います。
USB機器を多数使用していて机の上(PC周辺)をすっきりさせたい方にお勧めです。