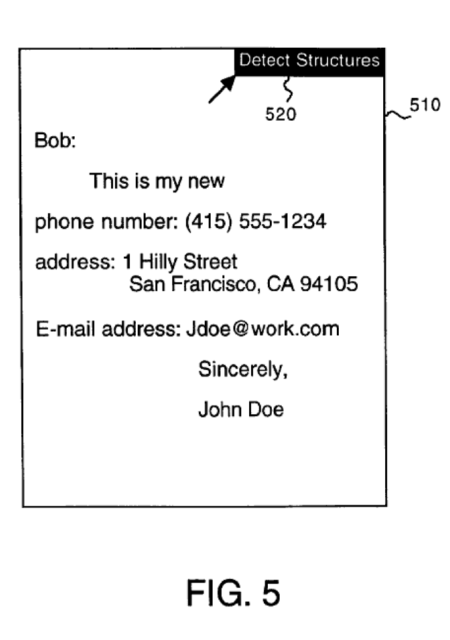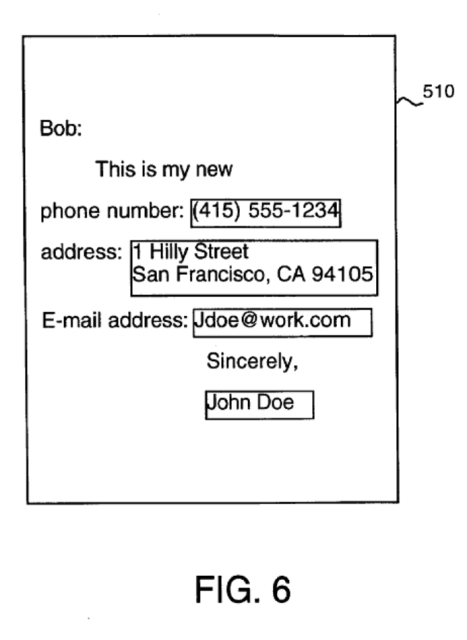息の長いブランドのひとつであるコンバースですが、現在は米国からの並行輸入が禁止されているようです。(参考togetter)。
理由は商標法上の問題です。ちょっと長くなりますが説明します。
商標の使用には生産や販売だけではなく輸入も含まれますので、日本において商標権を持っている人は許可なく輸入される商品を税関で差し止めることができます。偽ブランド品を国内市場に入る前に水際で規制するのは理にかなっています。
ただし、ここで、偽ブランド品でない本物の並行輸入はどうなるかという問題があります。これは「真正商品の並行輸入」という商標制度上の論点です。判例的には、いくつかの条件を満足していれば(商標の出所表示機能が損なわれているわけではないため)並行輸入は問題なしとされています。その条件のひとつが「内外権利者の同一性」です。たとえば、外国における商標権者と日本における商標権者が親子会社というような条件です。
これは、よく考えてみれば当たり前の話です。「内外権利者の同一性」という条件がないと、たとえば、日本のブランド(例としてセイコーとしましょう)の商標権がないマイナーな国で勝手に商標登録して、日本のセイコーとは何の関係もないボロ時計に「セイコー」というブランドをつけて販売し(これ自体はその国においては合法)、日本に輸入することが許されてしまいます。これでは、日本におけるセイコーの商標権は実質バイパスされてしまいますね。
ということで、通常のブランド品(本物)を海外で買って並行輸入する上で問題はないのですが、コンバースの場合には、一度倒産して伊藤忠が資本参加してコンバースジャパン設立、その後、本体はナイキに買収という複雑なな経緯をたどっており、現時点では日本の商標権者と海外の商標権者が同一ではないという事情があります(参考Wikipediaエントリー)。要するに米国のコンバースと日本のコンバースはブランドは同じでも別物ということです。
実は、この件は裁判になっており、日本の権利者の主張が認められています(参考ブログエントリー1、2)。
というわけで、一般消費者視点では米国コンバースは偽物という認識ではたぶんないと思うので腑に落ちないかもしれないですが、米国コンバース製品の並行輸入は違法ということになります。
なお、商標権は「業として」の使用にしか及びませんので、個人で使うために海外で買った商品を国内に持ち込む分には商標法的には問題ありません(もちろん、倫理的な問題は別です)。ただし、露骨な偽ブランド商品の場合には「任意」の放棄を要求される運用になっているらしいです(この辺は税関のサイトで文書化されているわけではないのでまた聞きレベルの情報)。もしこの「任意」の要求を断るとどうなるのかはそういう経験がないのでわかりません。また、一人で同じ商品を(特に箱入りのまま)何個も持っていたりすると、販売目的、つまり「業として」と判断されて没収されてしまうこともあるようです。前記togetterの情報でもコンバース3個持っていた人が税関で没収されてしまったようですが、まあこれはしょうがないかもしれません。