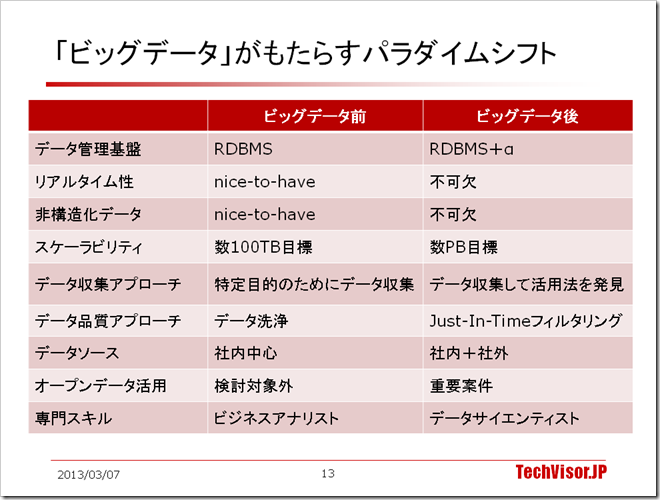クラウドソーシング型特許先行技術文献サーチサイトArticle Oneに関する記事はそこそこ話題になったようです。
具体的にどんな感じかを示すために、同社のWebサイトから直感的にわかりやすい課題(同社はStudyと読んでます)をひとつ引用して説明します。日本語サイトででのタイトルは「表示されている追加の文字に所定の期間の結果にキーを押すと特徴とする携帯機器用のキーボード」となっていて訳がわかならいので以下で具体的に説明します。
なお、同社の日本語サイトは日本語がめちゃくちゃ(機械翻訳?)ですし、求められている情報の中核部分はどっちにしろ英語なので、最初から英語サイトにあたった方がよいと思います。
では、この課題で求められている情報のサマリーを書きます(正確な情報はArticle Oneのサイトの情報を直接見てください)。
- 画面上にソフトウェア・キーボードが表示されている
- 普通に打つとキートップに書いてある文字が表示される
- キーをしばらく押していると関連する別の文字セットが表示される(たとえば、下図の絵のように、Aのキーをしばらく押しているとウムラウト付のăなどのミニキーボードが表示される)
- ミニキーボードから文字入力すると最初のキーボードに戻る

この機能は、今では当たり前のアイデアであり、iPhone/iPadのソフトウェア・キーボードでも実装されています(依頼企業は匿名ですが何となく想像がつきます)。
このようなアイデアが開示されている文献で2001年6月9日以前のものを発見するのが課題です。なお、サイトには既に発見済みの先行特許文献も書かれていますので、これら以外のものを探す必要があります。一番良質の情報を提供できた人は5,000ドルもらえます。
この2001年というのがくせもので、ITの世界で10年前はめちゃくちゃ昔なので、現在では当たり前の技術であってもそう簡単に証拠は見つかりません。2001年というとMicorosoftがタブレットPCを出荷する1年前です。タッチ操作はスタイラスペンが当たり前で指で操作なんて考え方はほとんどなかった時代です。
こんなの当たり前だと思っていても、調べれば調べるほど出願時点では実はそんな当たり前ではなかったのだなということがわかってくる特許だと思います。私も何回か先行文献探しの仕事をしたことはありますが、「これだいぶ前に見たわー」と思って臨んだもののその「だいぶ前」は実は結構最近で、特許の出願日よりは全然後だったなんてことがよくあります。まあ、そもそも出願時に誰でも知ってるようなレベルであれば、さすがに特許庁の審査官も特許査定出したりはしません。
一般に言えることですが、Article Oneの課題に対してGoogleサーチから始めているのでは賞金獲得は困難だと思います。依頼企業はほとんど米国だと思われるので英語資料はサーチしているでしょうから、日本語の資料、かつ、ネットにないオフラインの資料が狙い目だと思います。「昔、こういう機器開発して論文書いています」とか「異常に物持ちがよくて昔のWindows CE機の取説持ってるけどそこに書いてあります」というような人を探し出せるのがクラウドソーシングならでは意義と言えるでしょう。
文献を知っている方、発見した方は、私はArticle Oneとは関係ないので私に送ったり、このブログにコメントしたりしないで、直接Article Oneに送ってください。