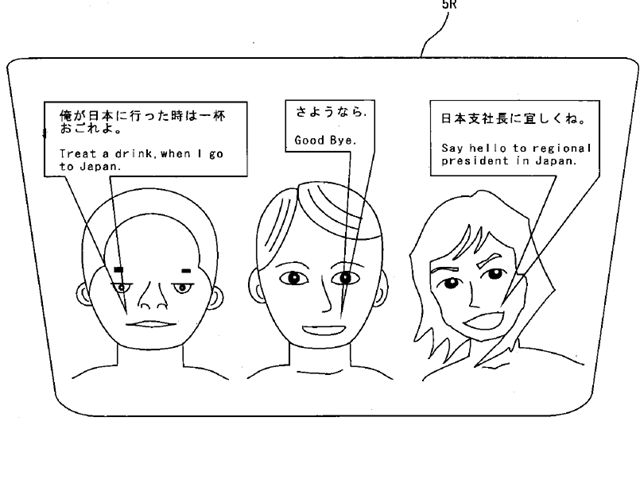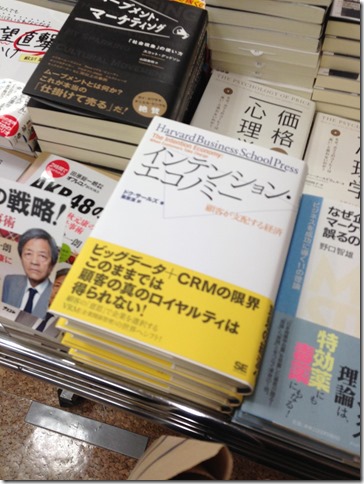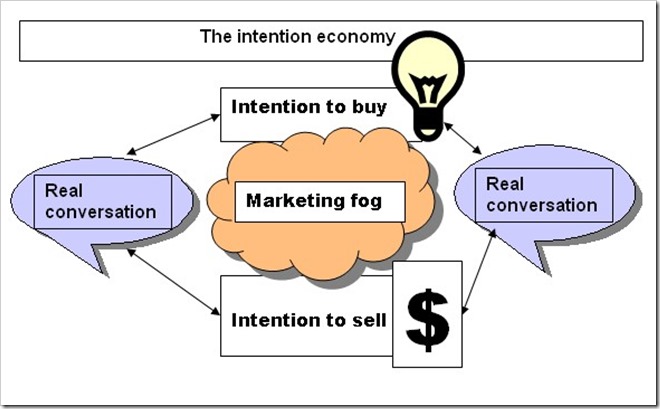MSNに「特許侵害とドコモ提訴 英領バージン諸島の企業」なんてニュースが出てました。
「iモード」などで使われている技術で特許を侵害されたとして、英領バージン諸島に本社がある「ユーペイド システムズ リミテッド」が25日、ドコモに100億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
ということです。100億円という切りのよい数字は何なんだと思いましたが、「1360億円超とする損害のうち一部を請求」ということだそうです。
原告であるUpaid SystemのWebサイトを調べてみると案の定思いっきりNPEでした。しかし、他社から特許権を買うことはせず、自社内の発明家のアイデアを特許化しているそうです。
では、どの特許なのかとIPDLで調べると「ユーペイド」名義で日本に出願されている特許出願は4件あります。すべて2002年の出願の分割出願で1件は拒絶確定、1件はつい最近(14/3/13)に登録査定、残り2件は審査継続中です。しかし、いずれも「1999年に出願され、2004年に登録された特許」という前記ニュース記事と合致していません。
可能性としては、社名が変わったか、M&Aしたかということになります。ユーペイド社の米国やWIPOへの出願を見ていると、発明者はだいたい共通なので発明者の中からカナ表記のぶれの少なそうな”Joyce, Simon James”を選んで「ジョイス サイモン」でIPDLで検索するとそれらしい特許3516339号が出ました(後で気づきましたがこの人がUpaid社のCEOでした)。
出願日は1999/09/14、登録日は2004/01/30(優先日は1998/09/15)、発明の名称は「通信システム」、権利者はInTouch Technologies Ltd.です。GoogleサーチするとこれがUpaid社の旧社名であることがわかりました(住所も英領バージン諸島なので間違いないでしょう)。
最初のクレームは次のようになっています。
【請求項1】
種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い、1以上のネットワークを介して、事前に許可された通信サービスや取引を提供するサービス提供方法であって、
前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて、ユーザから個人識別情報を受信するステップと、
前記個人識別情報を認証するステップと、
前記通信サービス、前記取引及び前記ユーザの口座情報を提供する前記機能拡張されたサービスプラットホームを介し、前記個人認識情報の認証の際に、該通信サービス、該取引及び該ユーザの口座情報のうち少なくとも1つの提供についての要求を、前記ユーザから受け付けるステップと、
前記通信サービス、前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取る権限を有するか、前記個人識別情報と関係付けられた口座が、前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証するステップと、
権限のある前記ユーザに対して、前記通信サービス、前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち要求されたものを、前記種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから、該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御して提供するステップと、
前記通信サービス及び前記取引のうち前記ユーザに提供されたものについて、前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して、権限のある前記ユーザの口座に課金するステップと、を含み、
前記機能拡張されたサービスプラットホームは、前記通信サービス、前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されていることを特徴とするサービス提供方法。
ということで分析するのはちょっと骨が折れそうです。
ところで、前述の発明者にしてUpaid社CEOのSimon Joyce氏の住所はバンコクになっています。他に10人以上も発明者がいますが1名はアメリカ在住で残りはインド在住(インド系の名前です)。また、Upaid社のサイトを見ると他のマネージメントがサンディエゴとベルギーにもいるようです。そして、本社は英領バージン諸島。なんか、こんなことを勝手に調べていると、謎の国際組織から狙われるのではないかとちょっと怖くなってきました(冗談です)。
追記(13/04/26):Simon Joyce氏についてさらに調べてみると(ソース)、タイでSinobrit Advanced TechnologiesというSIerを創業して成功、その前はThorn EMI Internationalという国防関係の情報技術の会社でアジア地区を担当、さらにその前は英国でバロースのセールスマネージャー(このことからそれなりの年齢であることがわかります)ということで、ITの実業で経験を積んだ人のようです。なんとなく、タイのホテルのプールサイドで日光浴しながら電話で世界各国に指令を出す黒幕みたいなイメージを勝手に持ってましたがそういうわけではなさそうですw
さらに、この発明はインドの大手ソフトウェア開発会社であるSatyamのエンジニアが協力したようです(その後の権利売却に関してUpaidとSatyamともめています)(ソース)。この特許の発明者であるインドの人々はSatyamのエンジニアだったということでしょう(UpaidのWebサイトの記載とちょっと食い違ってますが)。