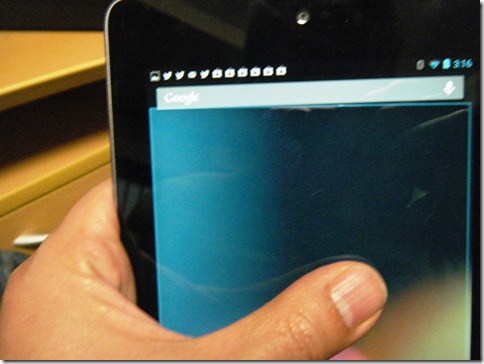昨日のエントリーでアップルがiWatchの商標をまずジャマイカに出願して優先日を確保しておいてから各国に出願する戦術を取っていると書きました。台湾、メキシコ、ロシア、トルコにも日本と同日に同じくジャマイカの出願に優先権を指定した出願を行なっているようです(参照記事(MacRumors))。
これがよくあることなのかちょっと調べてみました。
その結果を書く前に、なぜ、わざわざジャマイカに出願なんてことをするのかを説明しておきます。
まず、多くの国において商標は先願主義なので出願人としてはできるだけ早めに出願しておきたいという意図があります。特に世間の注目度が高いアップル製品などは噂が出た段階で商標ゴロ的な人が勝手出願(冒認出願)をする可能性が高いので早めの出願が不可欠です。
しかし、その一方で、商標登録出願をするとその内容が一般に公開されてしまうという問題があります。国により多少の差がありますが、出願すると1〜2カ月くらいで、商標の内容と出願人が世間に知られてしまいます。当然、アップル製品であれば誰かがブログ等に書けばあっと言う間に情報が広がってしまいます。アップルとしては製品発表前にブランド戦略が世の中に知られるのはあまり好ましくありません。
ということで、アップルとしてはできるだけ早く出願したい、だけど世の中にばれるのはできるだけ遅くしたいという相反するニーズがあります。
ここで、パリ条約という知的財産権に関する国際条約が定める優先権制度が利用できます。優先権とはひとつのパリ条約に加盟国に出願しておけば、それから一定期間内(商標の場合は6カ月)以内に他の加盟国に出願した時に最初の出願と同じ出願日として扱ってもらえる(つまり、出願日をできるだけ早めるというニーズに応えられる)制度です。複数国に出願する時に同時に出願しなければならないとするとあまりに負担が大きいのでこのような制度が設けられました。なお、あくまで出願日が遡及するというだけの話で、審査は国ごとに行なわれるので、ある国では商標登録されて別の国では登録されないということはあり得ます。
さて、最初にどこの国に出願するかですが、日本などのメジャーな国に出願すると公開されてネットで閲覧可能になってしまいます。一方、ジャマイカは公開された商標登録出願をネットで閲覧できないようなので(ジャマイカの商標局を訪れれば閲覧できるのかもしれませんが)出願内容が世間にばれにくいというメリットがあります。
ということで、まずはジャマイカに出願して優先日確保というのは理にかなった戦術です。実際、iWatchの日本での出願も出願日が2012年12月3日に繰り上がったことで、今年の1月〜3月の勝手出願(と思われる出願)の影響を受けなくなりましたし、iWatchという商標を出願していたこともぎりぎりまでばれませんでした。
では、他にこのようなパターンがどれくらいあるかを調べてみようと思ったのですが、日本の特許電子図書館(IPDL)も米国特許商標局(USPTO)の検索サービスもパリ条約優先権の第1国をキーとして検索することができません。もちろん、アップルの出願をひとつずつ調べればわかるのですがさすがにめんどくさいですし、アップル以外にこういうことをやっている会社があるのかは調べられません。
しょうがないので、WIPOの国際登録の検索サービス(ROMARIN)を使って調べてみました。パリ条約優先権を指定した出願が必ず国際登録されるとは限らないのですが、まあわざわざジャマイカに出願してなんてことをやるくらい重要な商標であれば国際登録もされているとみてよいでしょう。ROMARINのAdvanced Searchで”Data Relating to Priority”がJM(ジャマイカ)を含むという条件で検索してみると64件ヒットし、そのうち60件がアップルによるものでした。要はほとんどアップルでした。
重複分と図形商標を除くとこんな商標です。
JOINT VENTURE, ITUNES EXTRAS, ITUNES LP, Q, TUNEKIT, Made for iPad, Made for iPhone, Made for iPad iPhone, WebKit, Made for iPod iPhone, Made for iPod iPad, Made for iPod iPhone iPad, BRIEFING ROOM, AIRPRINT, RETINA, Lion, iAd, MISSION CONTROL, THUNDERBOLT, AirPrint, ICLOUD, STARTUP, SMART COVER, AIRDROP, ASSISTIVETOUCH, ITUNES MATCH, SIRI, GUIDED ACCESS, PASSBOOK, FLYOVER, EARPODS, IPAD MINI
では、Apple以外の4件はというとCiscoのIOSとCISCO PARTNER AWAREという商標、マイクロソフトの図形商標、Nestという会社のNestという商標です。
ついでに第1国がトリニダード・トバゴ(TT)のパターンも調べてみました。66商標中、Appleが35、Zyngaが18、あとは、Intel、Cisco、Avid等が少々という感じです。やはりアップルが多いです。国際登録しないケースもあると思いますし、ジャマイカとトリニダード・トバゴ以外の商標公開情報が検索しにくい国に出願するというパターンもあると思うので何とも言えない部分もありますが。
ところで、日本でも製品発表前に商標登録出願しておく場合、思ったより早く商標の出願内容が公開されてしまってネタバレというパターンにならないよう出願のタイミングには注意が必要です(ジャマイカに先に出願しておくほどではないにせよ)。商標を専門にやっている弁理士事務所であればこの辺のタイミングはアドバイスしてくれるはずです(もちろん、弊所でもアドバイスしてます)。