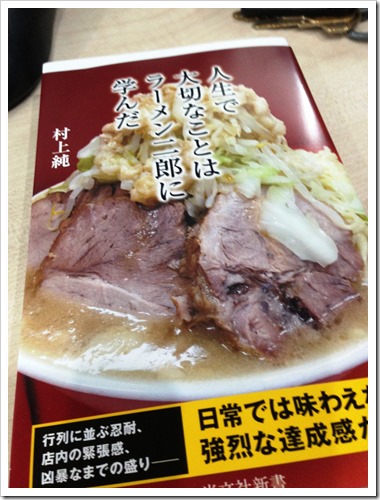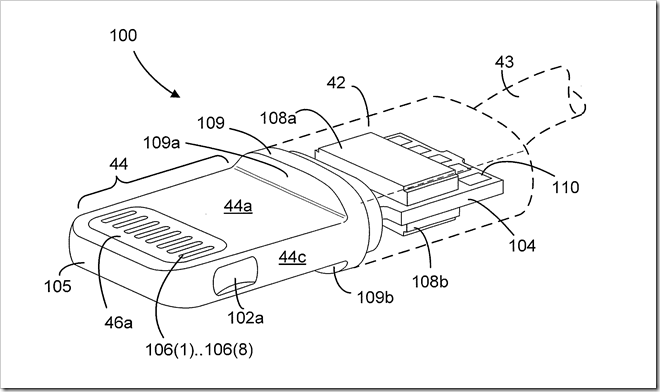東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。
個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日本の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。
ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。
「自炊」とは手持ちの本をスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。)
自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
このスキャン(複製)作業を業者に依頼すると「その使用をする者が」の条件が満たされなくなりますので、私的使用目的複製にはならず、その結果、(著作権者の許諾がない限り)著作権(複製権)の侵害になってしまうというわけです。
自炊代行業者による、原本は破棄するのでコピーは増えておらず、著作権者に実害は発生していないという主張は理解できないことはないのですが、やはり法文に明確に条件が書いてある以上、それを覆すのは厳しいものがあります(米国の制度ですとフェアユースの法理により柔軟に解釈され得るのですが、日本の著作権法にはフェアユース的な考え方はほとんどありません)。
「スキャン業者は利用者の手足として動いているだけなので『その使用をする者』に該当する」といった「画期的解釈」もないわけではないかもとちょっとだけ期待する部分はありましたが、そういうわけには行きませんでした。
自炊代行と同じ理屈で、手持ちのLPレコードをCD-Rに変換したり、レーザーディスク、VHS、8ミリビデオ等をDVDに変換してくれる代行業者も違法とされます(もちろん自分で変換する分には問題ありません)。これらのケースですと手間暇以前の問題にそもそも旧メディアのプレーヤーが入手しにくくなっていますので、変換代行業者のニーズはさらに大きいでしょう。結果として、たとえばCD化されていないレコード音源が死蔵されるケースが増えると著作権法の目的である文化の発展に反するのではないかという気もします。
これから知財高裁で争って別の結果が出る可能性もありますが、30条の規定については見直す段階に来ているのではないかと思います(ダウンロード違法化とかDVDリップ違法化とか制限を厳しくするほうではいろいろ見直しされてきているのですが)。
また、権利者側との合意により自炊代行業者が利用料を支払って許諾を受けるモデルの検討も進んでいます(一部権利者はそれでもいやだというかもしれませんが)。著作権法における「違法」というのは「権利者の許諾がなければ違法」(許諾さえあれば合法)というだけの話なので、良い落としどころが見つけられればとも思います。