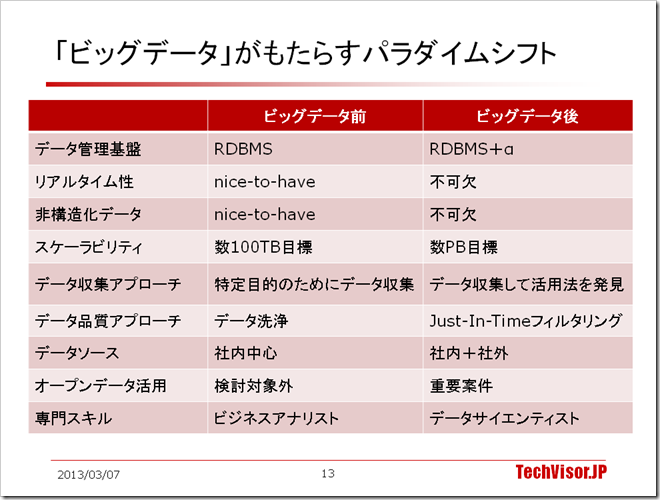特許庁の新システムの開発が頓挫して55億円が無駄になったというニュースは既によく知られています。特許庁は特別会計で運営されているのでこの55億円の出元は税金ではなく特許庁に出願人が支払ってきた料金なのですが、それでも国民の金であることに変わりはありません。加えて旧式化したシステムをしばらく使い続けなければならないということで、知財立国をめざす我が国にとって大きな痛手であります。
なんで、この話を今更持ち出したのかというと、昨日のTBSの報道特集でこの問題が取り上げられていたからです。番組では、開発に反社会的勢力がからんでいた的な話が中心になっていましたが、それに関する議論は別の方におまかせするとして、この機会に以前に書こうと思って書き忘れた話を書いておきます。純粋に情報システムとして見たときに特許庁のシステムはそんなに難しいのか、というお話です。
特許庁の内部事情は全然知らないので、特許庁審査官とのやり取り、そして、特許庁システム機能のWebフロントエンドであるIPDLのほぼ毎日の使用経験に基づいて書きます。
まず、特許庁のシステムの機能は大きくコンテンツ管理とワークフロー管理に分かれると思います。
コンテンツ管理システムとして見ると、大量の出願書類を管理することから、データ量は多いでしょう(基本的に過去の出願資料は全部保管しなければいけません)。それでも、年間30万件の出願を40年間保管、1出願あたりのデータ量が(余裕を持たせて)100MBとして計算すると120TBでしかありません。
さらに、ステータスや内容が変わるコンテンツはせいぜい過去10年分くらいで、それより以前はスタティックなコンテンツです。また、内容が変わる時には、ほとんどの場合、法律で決まった補正の手続きに従います。何を誰がいつ変更できるかは法律で決まっています。
また、コンテンツの形式も法律で決まってます。非構造化データではあるものの、そのスキーマはほぼ一定です。ユーザーが独自のスキーマを設定することはありません。もちろん、法律の改正による形式の変更はありますが、それはそれほど頻繁でもないですし、共通形式が決まっているという点は変わりありません。
次にワークフローです。特許庁の最も根幹的な業務は出願書類を審査して登録査定するか、あるいは、拒絶査定するかを決めるワークフローです。このワークフローもおおまかには法律で決まっています。たとえば、特許出願がされると、まず、方式審査が行なわれ不備があれば補正命令が出されます。問題がない、あるいは、不備が補正されると審査請求待ち状態になります。審査請求が出されると実体審査が始まります。出願から3年以内に審査請求が出されないと出願は自動取り下げになります、などなどです。
ワークフロー管理のシステムを構築する場合の難所は1)全体像が見えにくい、2)例外プロセスが多い、3)プロセスの最適化の検討が大変、等にあると思います。
特許庁のシステムの場合、1)全体像は既に法律や関連規則で文書化されています(特許法は実体法と手続法が一体化しており基本的な手続きは法文に書いてあります(たとえば、前述の3年以内に審査請求しないと取下げになるというルールなど))、2)特許庁内部での例外プロセスは数多いと思いますが根本的な部分は法律のルールに従わざるを得ません(たとえば、上記の審査請求の期間を担当者が勝手に延長することはあり得ません)、そして、3)プロセスの最適化(3年じゃなくて2年の方がいいんじゃないかというような議論)は法律改正の議論であってシステム設計時の時の議論ではありません(もちろん、システム上、法定期間を柔軟に変更できる設計にしておく必要はありますが)。
ということで、特許庁のシステムは、規模は多少大きいですが、グランドデザインが法律等で既に文書化されてる点で比較的御しやすいと思います。法律の条文、関連規則、特許庁の内部基準等々、文書は膨大ですが、既に文書化されているというのはワークロード管理システム開発者にとっては大変にありがたいことです。
逆に言うと法律の知識なしにボトムアップ式にワークフロー分析を始めると結構大変かと思います。「報道特集」では匿名の関係者が「開始直後から開発チームが現場担当者にインタビューしてスプレッドシートを作成していたがとても使えるものじゃなかった」という趣旨の発言をしています。
たとえて言えば、都市計画を行なう時に、航空写真や地図があるのに誰も見方を知らないので一生懸命に個別の家の設計図を分析しているようなものでしょう。頓挫して当然という気がします。逆にグランドデザインを理解している人が開発リーダーにいればそれほど困難な案件とは思えません。
ところで、「報道特集」では、韓国の特許検索システム(日本だとIPDLにあたるもの)がスマフォ対応しているのが紹介されていました。日本のIPDLはこれと比較すると恥ずかしくなるようなダム端末的UIです。
そういえばマドプロ経由で韓国に商標登録出願して韓国特許庁からOAが出るとWIPOから通知が来る前に、韓国の特許事務所から「うちにOA対応やらせて」というメールが多数届いたのですが、たぶん、リアルタイムでアラート設定できる仕組みがあるのでしょう。
米国もパーフェクトというわけではないですが、そこそこモダンなUIでリアルタイム性の高いサービスを提供しています。そして、民間企業で実績のある人物をCIOに置いてシステム改革を進めています。
日本はとんでもないハンディキャップを負ってしまったと感じます。