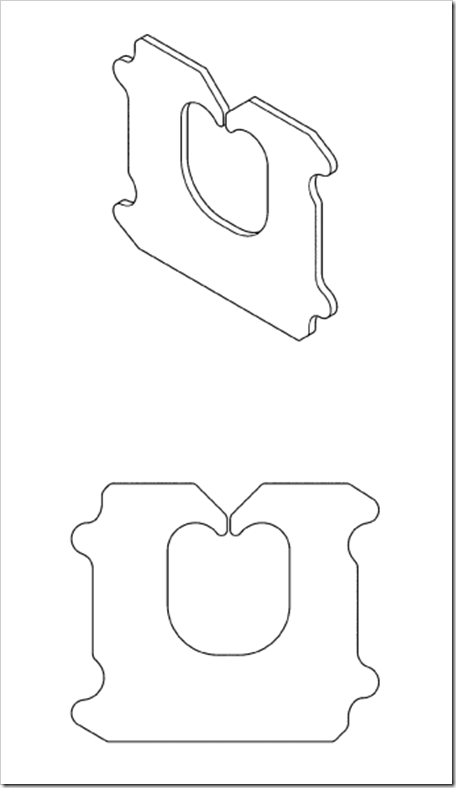先週の金曜日から大腸憩室炎で入院中です(4年ぶり3回目)。憩室炎というのは、加齢によってできる大腸のくぼみのような部分(憩室)が炎症を起こす病気です。病気の性質という点では盲腸のような感じで早めに対応すれば何の問題もないですが、こじらせて腹膜炎を併発したりするとどえらいことになるので注意が必要です。カンニング竹山がちょっと前にこの病気で入院してましたね。
50歳を越えると多くの人に憩室ができるそうなので、憩室炎のリスクは誰にでもあります。単なる食あたりかと思って病院に行くのが遅れると大変なことになることもあるので、早期の判定が重要です。
自分の経験から言うと、まず、普通の食あたりであればお腹を押すと痛みが和らぐことが多いのですが、憩室炎の場合、かえって痛くなります(特に押した状態から離した時に痛みが来ます)。また、下痢ではなく、腹が張る感じになり、吐き気がします(自分が最初にこの病気になった時は、吐き気から「腸閉塞?」と思って救急車呼んだのが幸いしました)。微熱が出ることも多いです。
治療は、絶食、安静、抗生物質です。絶食が必要ということは点滴が常に必要ということなので通常は入院するしかないですね。
現在は、別に熱が出て頭がぼ〜としたりとか、痛みで死にそうだとかいうわけではなく、単に点滴しているだけなので病院で普通に仕事しています。出願案件は電子証明書の関係で仕事場のPCからでしかできないので外出許可をもらってやってます(インターネット出願ソフトも早くクラウド対応して欲しいものです)。
このブログも病室のベッドで書いています(iPhoneのテザリング使用)。WiFiのアクセスポイントをサーチすると”xxx’s iPhone”というSSIDがいくつかあることから同じように病室でWiFi使っている人も多いようです。電波が機器に影響をーなんて話も昔はあったようですが、現在では、ほとんどの病院が(おそらく緊急病棟等をのぞき)WiFi OKになていると思われます。
どうせなら有料でもよいので病院でもWiFiのサービスを提供して欲しいものです(それとUSB充電ポート)。
ところで今回は症状が比較的軽かったので普通に外来に行ったら、即CTと血液検査で即入院(白血球跳ね上がってました)ということになりました。前回は救急車呼びましたが、10分くらいで来てくれてすぐ救急病院ディスパッチして即CT検査で確定診断(そのまま入院)です。これらすべて健康保険内ですんでしまうわけで、日本の医療制度ってすごいですよね。これがいつまで続くのかわかりませんが。
一部の方には仕事の遅滞でご迷惑をおかけするかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。