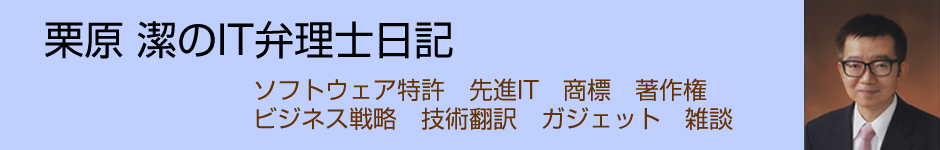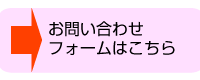クリープハイプというロックバンドのベスト盤をレコード会社が勝手に販売したことがちょっと問題になっています(参照記事)。
こういう事件は今までもありました。上記記事には宇多田ヒカルの例が載ってますが、それより前にはYMOの事件が有名です(関連フラッシュ)。
これらのケースで具体的にどのような契約が結ばれているのかはわかりませんが、ネットで公開されている専属実演家契約書(レコード会社とアーティストの間の契約書、別名、録音契約)のひな形を見るとだいたい想像がつきます(このひな形は「よくわかる音楽著作権ビジネス」の著者として有名な安藤和宏氏が代表をやっている会社Septima Leyのサイトに載っているものです)。
ここで問題になるのは著作権ではなく、著作隣接権のひとつであるレコード製作者の権利(通称、原盤権)です。著作権は作曲家・作詞家がJARACに信託していますので、特定の利用形態に対してNoということはできません(もちろん、JASRACとの信託契約を解除することもできますが、そうするとJASRACからの著作権利用料がいっさい得られなくなりますので非現実的です)。
上記のひな形契約書によれば、原盤権も含め一切の権利を甲(アーティスト)は乙(レコード会社)に譲渡することになります。なので、アーティスト側はいったんレコーディングされた楽曲の利用についてはコントロールできません。
第3条(権利の帰属)
1. 乙は甲に対し、本件原盤に係る乙の実演についての著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
ただし、どういうCDを発売するか等は、アーティストとレコード会社が協議の上決めることになっています。
3.レコード、ビデオおよび音楽配信の種類、価格、発売日、販売方法その他一切の事項については、甲乙が協議の上、決定するものとします。ただし、レコードおよびビデオの数量については、甲乙が協議の上、甲が決定するものとします。
さらに、アーティスト側にとってちょっと厳しい条件は以下です。
第12条(保証)
…
3. 本契約終了後 3 年間は、乙は、本契約に基づいて実演した著作物と同一の著作物について、甲以外の第三者が行うレコーディングのための実演を行わないものとします。
同じ曲でもレコーディングをしなおせば原盤権は新たに生じますので、原盤権を自分で持つなり、別のレコーディング会社に渡すなりすればよいのですが、それはこの契約終了後の3年以内はできないという条件です。
クリープハイプのケースでは、「ベスト盤は、タイトル、収録曲、アートワーク、発売日、特典すべてをレコード会社が一方的に決め、メンバーにも事務所にも一切連絡がなかった」そうなので、もし上記の協議義務が契約書に書いてあれば、契約違反に問える可能性はあると思います(もちろん、あくまでもひな形の条項をベースに議論してますので、実際の契約書に書いてあるかどうかはわかりません)。
これだけ見るとずいぶんアーティストが不利なように見えますが、レコード会社は投資をして金銭的リスクを負う立場である点も考慮する必要があります。
さらに重要な点はこれはアーティストも納得の上で合意した条件であるということです。民法の大原則、契約自由の原則がある以上、納得の上合意した条件に従わなければいけないのは当然です。
企業の労使契約のように契約自由の原則だけに任せておくと一方が圧倒的に不利になってしまう場合は別ですが、音楽アーティストの場合はいくらでも選択肢があるわけなので、契約条件(特に、著作隣接権を全部譲渡する件と再レコーディングの3年間禁止の件)が気に入らなければ、再交渉するなり、もっと良い契約条件を提示してくれるレコード会社(典型的にはインディーズ)を探すなり、自費制作するなりすればよい話です。