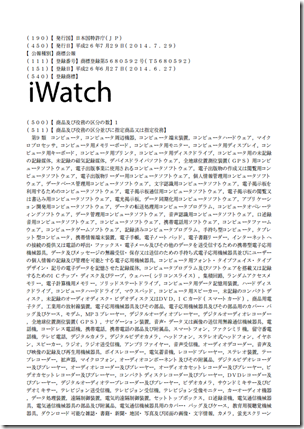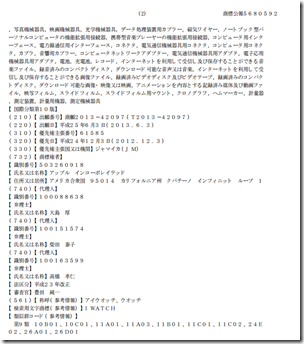前エントリー(重要追記あり)で書いたとおり、Appleは一部の国で商標権を取得できているにもかかわらず、iWatchの名前を捨ててApple Watchとすることを選んだわけですが、別の会社が時計を指定商品にしてAppleという商標を既に登録してないかちょっと気になりました。たとえば、中古車買取企業のように「アップル」という社名・商標はありがちですなので。自社名+商品の普通名称というパターンなので商標権の効力は及ばない(商標法26条)とは思いますが一悶着起こる可能性がないとは言えません。
ということで、日本国内に、時計に類似する商品を指定した「Apple」という商標登録・出願がないか調べてみたら1件だけありました。Apple Inc.自身によるものが。
かなり前の2012年5月25日に出願された登録5631909号です。このような事態を読んだ上でのプランBだったんでしょうか(ちなみに「アップル」でも登録されています(登録5563127号))。
この商標登録の指定商品は以下のようになっています。
7 金属加工機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置
10 睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,耳かき11 暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,太陽熱利用温水器,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類
14 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,記念カップ,記念たて,時計,デジタル時計
16 プラスチック製包装用袋,印刷物,写真,写真立て
17 ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,電気絶縁材料,ゴム製包装用容器,コンデンサーペーパー,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム
20 カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ
35 職業のあっせん,新聞記事情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
38 コンピュータネットワークへの接続の提供,データベースへの接続用回線の提供,映像・音声・データの伝送交換,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
39 輸送情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送
40 金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,金属加工機械器具の貸与,材料処理情報の提供,家庭用暖冷房機の貸与,家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,発電機の貸与
41 アナログ写真のデジタル化及びこれに関する情報の提供,移動体電話より送信された画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,デジタル画像処理に関する情報の提供,写真画像データの記憶媒体への複製,技芸・スポーツ又は知識の教授,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供,運動用具の貸与,写真の撮影
45 地図情報の提供,ファッション情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた友人探し・紹介・親睦のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,個人に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,インターネット上でのウェブサイトを通じたソーシャルネットワーキングユーザー向けの友達探し及び紹介のための情報の提供
日本の商標制度では確実な使用意思がなくても商標登録出願はできてしまうので、Apple Inc.がこれらの商品について「Apple」という商標を使う予定があるのかどうかはわかりません。少なくともアップルブランドの「耳かき」が出る可能性は低いとは思いますが。
実は、それ以外にもApple Inc.は日本において様々な商品とサービスについて結構な数の「Apple」あるいは「アップル」の商標登録・出願を行なっており、抜かりはないようです。