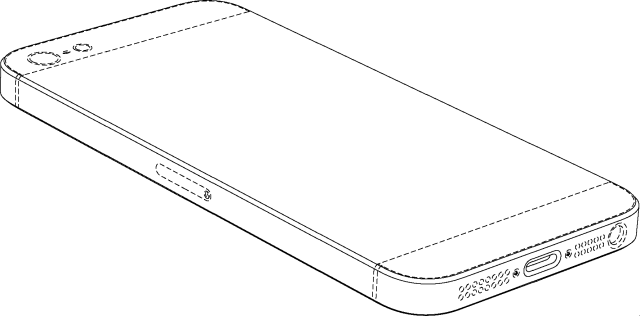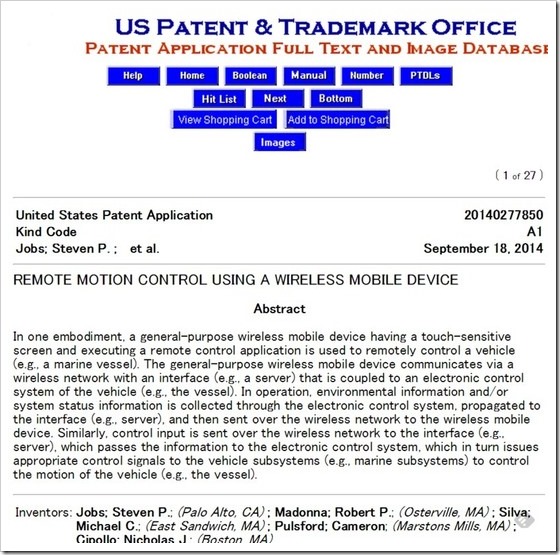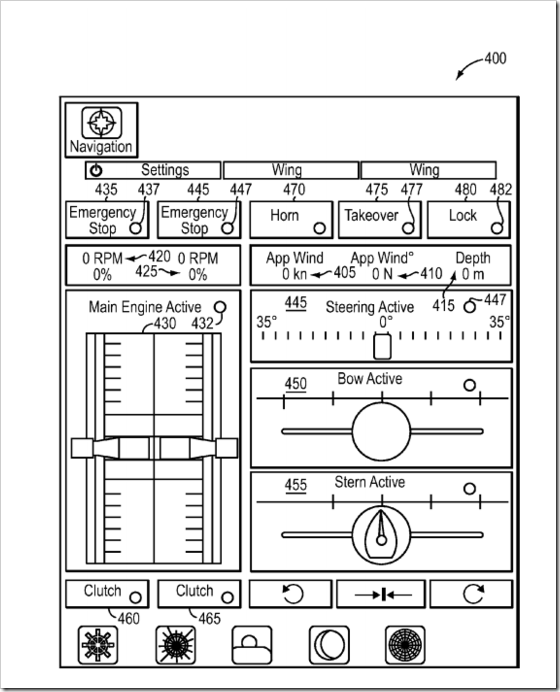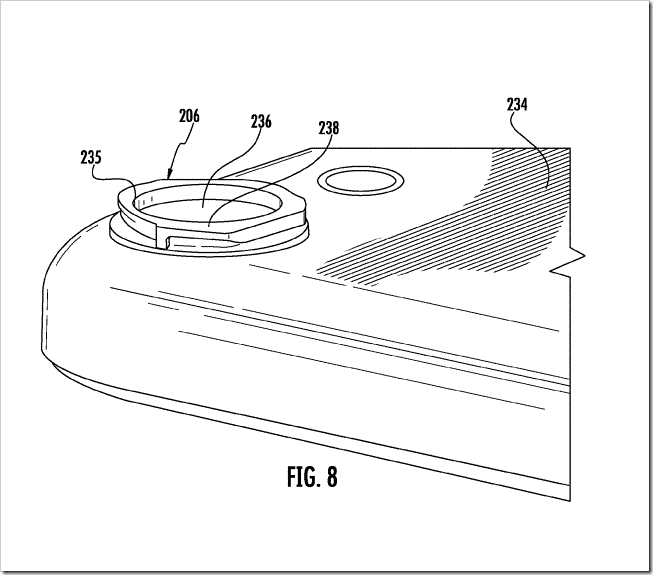ちょっと前になりますが、神奈川県が観光振興目的でファレル・ウィリアムスのヒット曲HAPPYを使った「踊ってみた」動画を作成し、Youtubeで公開しようとしたところ、権利者との折り合いがつかず楽曲使用を断念したというニュースがありました(参照記事)。税金を使って制作しているのですから、事前の権利クリアランスはちゃんとやってほしかったですね(著作権切れ楽曲のI Got Rhythmを代わりに使ったので動画がまったく無駄になったわけではないようですが)。
なんで、HAPPYが無料で使えるという勘違いをしてしまったかというと、以下の2つの可能性があると思います。
1.非営利だから権利者の許可はいらないと思ってたのではないか
確かに、日本の著作権法の規定では非営利・入場無料・ノーギャラの上映・上演・演奏は自由に(権利者の許可なく)できます(本ブログ関連過去記事1、本ブログ関連過去記事2)。ただし、これは、上映・上演・演奏だからこその話なのであって、Youtubeにアップするのは公衆送信(送信可能化)という利用行為なので別の話です。上映・上演・演奏は、その時1回限りで後に残らないので権利者の許可がいらない規定になっているわけです。
観光振興目的が非営利かという議論はあると思いますが、それ以前に公衆送信なので非営利目的であるかないかにかかわらず権利者の許可は必要です。
著作権法は利用行為(複製、上映、演奏、公衆送信等々)によって、規定が微妙に異なるのでややこしいです。この辺を把握していないで、QAサイトやブログのコメント等で、間違ったことが書かれているケースがたまに見受けられるので注意が必要です。
2.以前に「恋するフォーチュンクッキー」の踊ってみた動画がOKだったので「HAPPY」もOKだと思ってたのではないか
「恋チュン」のCD音源を使った動画をYoutubeに無料でアップできたのは著作権法上認められているからではありません。権利者がOKだと認めているからです。非営利ならOKと言うのは著作権法の規定には関係なく(前述のとおり公衆送信には営利・非営利は関係ありません)、権利者が決めた条件です。
HAPPYについては、他の都市から個人投稿の動画はOKとされていたそうですが、これも著作権法の規定とは関係なしに、権利者が黙認していただけの話です。
たとえば、仮に権利者が福島の復興目的でYoutubeにアップするなら営利目的でもOKだけど、それ以外は非営利でもダメだよという条件をつけてもそれは権利者の勝手であり、他者はそれにしたがう必要があります。
タイトルの質問「なぜ「恋チュン」は良くて「Happy」はダメなのか」には著作権法の規定には関係なくて「権利者の勝手」というのが答になります。
一般論として、誰かが他人の著作物を無料で利用しているように見える時、それが権利者の許可不要と著作権法で定められているからなのか、あるいは、権利者が(黙認も含めて)OKしているからなのかを区別するのは重要です。

 第1737946号
第1737946号 第872064号
第872064号 第989999号
第989999号 第990000号
第990000号