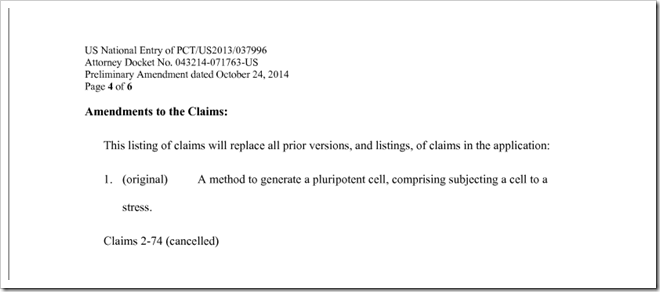過去記事「Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか?」において、AppleがiWatchの商標使用をあきらめたのは、スウォッチ社の登録商標iSwatchとの問題ではないかと書きました。しかし、どうもそれだけではなさそうです。
Bloombergの記事「アップル、“iWatch”はダメと新興企業が釘-商標登録済み」によると、イタリアの小規模ソフトウェア会社Probendiが欧州共同体において“iWatch”の商標権(指定商品はコンピューター関連機器とソフトウェア等(9類))を所有しており、Appleに対して警告してきたそうです。この商標登録は、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)が管轄する欧州共同体商標というもので、欧州共同体に属するすべての国で有効な商標登録です。
実際、Probendi社のウェブサイトには、欧州共同体内で“iWatch”の商標を使用できるのは当社だけであり、不正使用には法的措置を取るというようなことが書かれています。
同社は、過去にiWatchという名称のソフトウェアをイタリアの警察等に提供していたようなので、不使用取消審判も難しいでしょう(欧州共同体商標は欧州内のどこかで使っていれば不使用取消を免れるので、その点有利です。)
さらに、冒頭Bloombergの記事では、
同氏(Probendi社創業者)はiWatchの商標をフルに生かす考えだ。この名前のウエアラブル端末を開発する計画で、低価格での生産を目指し中国を訪れる。349ドル(約3万7700円)のアップル・ウオッチに対抗するつもりだ。
と書かれています。Appleとしてはちょっといやな感じでしょうが、あきらめるしかないでしょう。Probendi社側としても、こんなあまりメリットのないいやがらせのようなことをするよりもAppleに商標権を買い取ってもらった方が得策だと思うのですが、商標権譲渡の交渉がうまくいかなくてこうなったのかもしれませんし、今後の商標権譲渡を有利に運ぶための牽制としてこういう行為をしているのかもしれません。
そもそも、「i+普通名称」のパターンを製品名に使っていくというジョブズのプランは2つの理由によりちょっと無茶でした。第一に、先を読まれて誰かに抜け駆け出願されてしまう(iPadの時もAppleは苦労しましたね)リスクがありますし、第二に、たとえば、インターネット対応した製品やサービスの通称として頭にiを付けるのはありがちなので不正の目的はなくても偶然の一致があり得ます。
実際、OHIMが提供するTMView(欧州内だけでなく多くの国の商標を横断的に検索できます)で検索すると、抜け駆けが偶然かわかりませんが、iAuto、iRing等々、数々の「i+普通名称」パターンの商標登録・出願が行なわれています。Appleにとっては、今後は「Apple+普通名称」のパターンの方が全然楽でしょう。
一般に、企業名をできるだけ造語にして、企業名そのものを(いわゆるハウスマークとして)商標登録し、サービス名は「企業名+普通名称」とする(たとえば、Googleや楽天のようなパターン)のが、会社の成長・拡大に応じて、長期にわたって確実に商標登録を行なって行くために有効です。Appleは造語ではないですが、以前書いたように広い範囲で商標権を取得しているので一応安心と言えます。