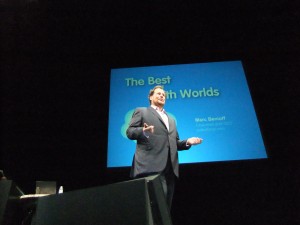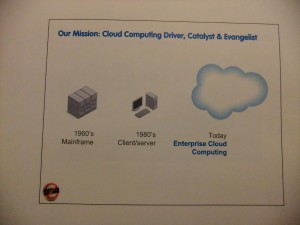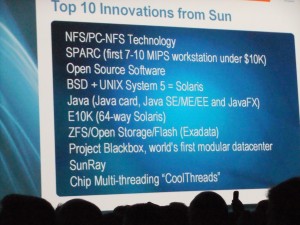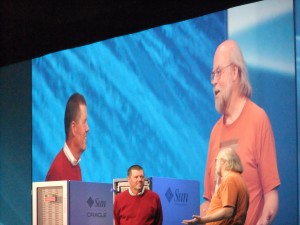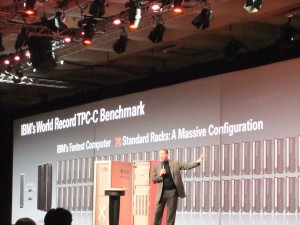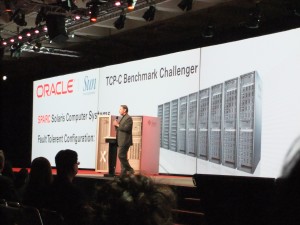ラリーエリソンの基調講演により、Oracle Open Worldが終了しました(イベントはもう1日残っていますがメディアの取材日は終わりました)。OOWでエリソンが何を語ったかについては、他の多くのメディアの人が書くと思いますので、私は「何を語らなかったか」について書こうと思います。
「語らなかった」ことの中で最大のトピックはやはりクラウドでしょう。今回のOOWでは、あたかもクラウドがNGワードになっているかのようでした。あるセッションでCLOUDというスライドが出てきましたが、講演者が「これはOracleの検閲通ってるから大丈夫だよ」とジョークを言ったほどです。そして、そのスライドの内容もプライベート・クラウドに関するものでした。
もちろん、OracleはCRM on DemandなどのSaaSビジネスもやっていますし、Amazon EC2のインスタンスでOrcale DBMSをサポートする等、テクノロジー的にもクラウドをサポートしています。しかし、ビジネス戦略としてはかたくなにクラウドを拒否しているように見えます。
この理由は明らかで、クラウドビジネスに乗り出すことが、Oracleの既存ビジネスモデルに与える影響を無視できないということです。言うまでもなくOracleは企業に対してソフトウェアを販売し、ライセンス料金と保守料金で収益を上げる会社です(これから先はハードウェアも収益になってきますが)。顧客の維持さえできれば最も高利益率のビジネスモデルのひとつです。オラクル的にはこのビジネスモデルをしばらく守りたい、そして、十分に守っていけると思っているということでしょう。
では、同じようなビジネスモデルのマイクロソフトがなぜAzureに乗り出したかですが、これは、同社がソフトウェアライセンス料金中心型のビジネスモデルにそろそろ限界が来たと感じたからでしょう。実際、デスクトップOSやOfficeスイートに依存して成長していくのはますます困難になっていくと思います。このような過去にとらわれない切り替えの速さはマイクロソフトならではと思います。
もちろん、オラクルもいずれはクラウドに大々的に乗り出す可能性は十分にあります(エリソンがクラウドのモデルをまったく評価していないのであればSalesforce.comに投資するわけはありません)。実際、Fusion Applicationはセルフサービスの管理機能を提供することでSaaS-readyであることを売りのひとつにしています。来年か再来年のOOWでは、Oracleが大々的にクラウド戦略を打ち出してもまったく驚くことはないでしょう。