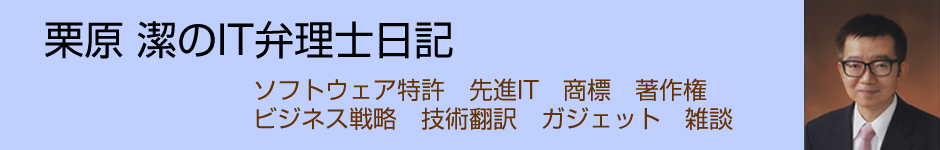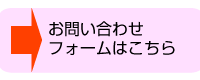ちょっと前になりますが知財高裁によって井村屋グループに「あずきバー」の商標登録が認められたというニュースがありました(正確に言うと、商標登録を認めないとした特許庁の審決を知財高裁が取り消したのですが結果的には同じことです)。
商標法には、商品の産地、材料、形態、効能等々を普通に表示しただけの商標(記述的商標と呼ばれます)は登録されないという規定(3条1項3号)があります。要は「そのまんまの商標」は登録されないということです。根拠は、そういう商標では消費者が他の企業の商品との区別を付けられず商標の機能を発揮し得ないこと、および、特定企業にそのような商標を独占させることは好ましくないことです。たとえば、特定企業が自社のオレンジジュースについて「オレンジ」という商標を登録して独占するのは明らかにまずいことから、この規定は当然と言えます。
しかし、この規定には例外があります。長年の使用によって、消費者が商品の出所を把握できるほどにおなじみになったと判断された場合には記述的商標であっても登録されます(3条2項)。「使用による識別性」とか「特別顕著性」と呼んだりします。使用による識別性を獲得した例としては「夕張メロン」などがあります。駄目だった例としてはサントリーの「はちみつレモン」などがあります(なので、他メーカーも問題なくはちみつレモンという名称の飲料を販売していたりします)。
「あずきバー」をあずきの入ったアイスバーという商品に使うと基本的には「そのまんま商標」なので登録できないという特許庁の判断は当然かと思います。問題は、「あずきバー」と聞いた時に消費者が井村屋の特定商品を思い浮かべるか、あずきの入ったアイスバー全般の名称としか考えないか、つまり「使用による識別性」があるのかないのか、という点です。
井村屋は知財高裁において「あずきバー」は既にナショナル・ブランドと言えるほど著名になっていること、多大な宣伝費を投資してきたこと等々を様々な証拠に基づいて主張して「使用による識別性」を認めてもらえました(なお、「あずきバー」はそもそも記述的商標ではないという主張も行なっていますがこちらは認められていません)(知財高裁の判決文(PDF))。
米国の商標制度にも「使用による識別性」と同様の考え方があります。一般に、セカンダリー・ミーニング(二次的意味)と呼んだりします。
セカンダリー・ミーニングのあるなしで今まさにもめている事件が、AppleとAmazonの間のApp Store商標の問題です。Appleは、多大な投資によりApp StoreはAppleのサービスというセカンダリー・ミーニングを消費者の間に確立させているので、Amazonがこの名称を使うこと(Amazon Appstore)を虚偽広告に相当するとして訴えました(米国では商標を使用しているだけで権利が発生するので日本とちょっと事情が違います)。これに対してAmazon側は「アプリのストア」なんだからApp Storeは「そのまんまの商標」であってAppleが独占すべきものではないと反論しました。
この争いについては、つい先日(2013/01/02)に、北カリフォルニア地裁が、Appleの訴えは根拠がない(AmazonがAppstoreという名称を使うことに問題はない)との略式判決を出し、その後和解を勧告しています(参考記事)。Appleの旗色が悪そうです。
個人的には「あずきバー」商標を井村屋に独占させるのは問題ないと思いますし、App Store商標をAppleに独占させるのはちょっとまずい気がしますのでいずれのケースも納得がいきます(人によって意見は違うと思いますが)。
ところで、商標権に関する争いにおいて、上記のように宣伝等に多大な投資を行なった企業が有利に扱われるのは不公平なんじゃないのと思われる方もいるかもしれません。しかし、商標制度とは本質的にそういうものなのです。この点で特許とは根本的に違います。
特許制度は個人のアイデア(発明)を保護するための制度です。したがって、多大な研究開発投資を行なっている大企業の発明も、町の発明家の発明も(少なくとも建前上は)同格に保護されます。しかし、商標制度が保護する対象はアイデアではなく企業の信用です。したがって、多大な宣伝費をかけてきた製品の商標には保護するに値する企業の信用がより強く結びついているので、より強く保護すべきであるというのが商標制度の基本的考え方です。
特許は創造活動(発明)の奨励を主な目的とし、商標は業界秩序の維持を主な目的とすると考えるとわかりやすいと思います。